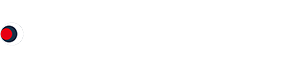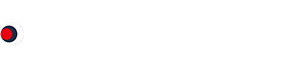図 書
剣道みちしるべ
第10回 ″三所避け″はなぜ悪か
総務・広報編集小委員会(当時)
真砂 威
今回は″窮極のまもり″といわれる、左拳を頭上に上げ体を右一重にする防御姿勢について考えてみましょう。ちまたで「三所避け(隠し)」「三方守り」と呼ばれる完全防御をねらった姿勢です。
その「三所避け」は十何年か前、某高校がこの防御姿勢を最大限活用して全国優勝を遂げてから流行が始まったとされています。それ以前においても、あの防御姿勢が皆無だったわけではありませんが、この話は後に回すことにします。では、なぜあの防御姿勢がいけないとされるのでしょう。古流などの伝書には、あの姿勢と同じような構えがよく出てきます。今われわれが行っている「日本剣道形」には、上段・中段・下段と八相・脇構えがありますが、古流にはもっとたくさんの構えが存在しました。しかし、現代剣道で使われている構えは、ほとんど中段のみで、上段に構える剣士は少なく例外的といってよいでしょう。どうやらこのあたりに問題解決の糸口がありそうです。

「八(重)垣」(『新陰流兵法目録事』より)
江戸時代の中期に、現代のような竹刀と 防具が考案されたことにより、竹刀打込稽古がはじまったと言われています。それまでふつう剣術の修業は「型」稽古によって行われていました。しかし戦闘なき時代を迎えたことで、実際の刀を使っての勝負はほとんどなくなってゆきました。そんななか「型」剣術は、実戦からしだいに遠ざかり、見栄えを競う華美なものへと変容をきたしました。そこで「治に居て乱を忘れず」とばかり竹刀打込稽古法が台頭してくるわけです。防具に身を護られ安全は確保されているものの、真剣勝負さながらの竹刀打込稽古は、競技的興味も加わり徐々に主流となっていきます。また、打突部位を「面」「小手」「胴」「突き」に限定させることも、安全性と競技性を高めようとする時代の流れのなかで必然的に行われました。そもそも防具は、甲冑を基に考えだされたもので、身体の要所を保護するものです。甲冑戦においては斬突不能の部位を、竹刀打込稽古では、逆にそこを打突することが″一本″になるという、いわば″ポイント制″が導入されたわけです。打突部位を四つに限定するということは、″攻防″の関係でいえば、攻めるに不利で防ぐに有利ということになり、その気になれば完全防御が可能となります。ここに現在における「三所避け」問題の根源があると思われます。
しかしその当時においては、競技化といっても″真剣勝負″が前提にあってのことです。打突部位の限定に合わせて、「構えや動き」にも制限を加えました。こうした条件を定めることによって攻防の緊張度を高め、精神性において″真剣味再現″をめざしました。もちろん当時には競技規則のようなものはありません。″黙契″といいますか、暗黙の了解で行われたのでしょう。
本誌本年(2008年)1月号の「新刊紹介」図書、『武道における身体と心』(前林清和著・日本武道館発行)では、ここのところを「実戦場面での心理的追体験」という表現をしています。同書は、
〈打突部位を限定することにより、無駄な動きを省略し、「面」を中心とした攻防の技で相手と対峙し、心理面を含めた優劣を競い合う、という競技方法を採っているのだと考えられる。打突部位が限定されているからこそ、相手が攻めてきても動じない、下がらないでぎりぎりのところまで耐え凌ぐ、心の深層から湧いてくる恐怖心や情動を抑え、精神的な安定、深化を目指そうとする。使える技を限定することによって、心理的緊張状態を高め、その中でいかに不動心、平常心をわがものとし、精度の高い攻防打突を達成していくか、そこが現代剣道の鍵となっているのである。〉
と述べています。
「真剣勝負」―この言葉は、剣と剣を交えた戦いのように、極度な緊張状態で向かい合う場面を表現する日常語として、今もよく使われています。「一所懸命」や「必死」よりつよく″いのちがけ″の響きが伝わってきます。これぞ日本精神の粋。まして真剣味再現をめざす剣道試合に、「三所避け」はおよそ似つかわしくありません。
(つづく)
その当時は「防具」や「剣道具」という用語はなく、それに相当する語としては、「道具」「武具」「竹具足」「竹鎧」といった語が用いられていた。
*この『剣道みちしるべ』は、2007年8月〜2010年1月まで30回に渡り月刊「剣窓」に連載したものを再掲載しています。