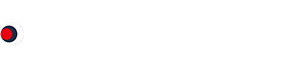図 書
剣道みちしるべ
第25回 節操の危うい国、日本
総務・広報編集小委員会(当時) 真砂 威
「侍の国、日本」・「道徳の国、日本」・「道について」と、3回にわたって日本人特有の心性について述べました。
そして、一般的に宗教教育が行われていないわが国で「道」の観念が衰退したら国民の道徳心が地に落ちるのは当然であり、今わが国はその状態に陥っている、と締めくくりました。
今回は、同じ日本人に内在する、これまで述べたとは全く正反対の性質について取り上げてみたいと思います。
昔も今も日本人は、キリスト教やイスラム教などの一神教の国の人たちと比べると、きわめて宗教的にあいまいです。神社の中に寺をつくったり、神前で読経したり、寺院の境内に守護神を祭って鎮守としたりしています。卑近な例をあげれば、年末にクリスマスを祝い、大晦日にはお寺で鐘をつき、翌朝の元旦には神社で柏手を打ちます。また、結婚式は教会で、七五三は神社、葬式はお寺でということはごくふつうに行われています。
日本人にとってそれらのことは宗教としてではなく、それぞれ使い分けて儀式や祭事の慣習としてこなしています。そういう面では懐が広いというか、非常に融通無碍な国民であります。
古代からわが国には「八百万の神」といって、森羅万象に神の発現を認める習わしがあります。いわゆる「多神教の神」です。またこの神は仏教、神道とも習合し、それぞれ分け隔てなく信仰されてきました。このことが他の宗教を大らかに受け入れられる素地となっているのだと考えられます。
この大らかさを広く世界に発信することをもって″世界平和″に結びつけたいと考えるものですが、小欄にはいささか荷が重すぎるようです。
しかし、このようなふるまいは、一神教の人たちから見たら原理・原則のない不可解、不思議な世界で、節操のない所行としか映らないのでしょう。
たしかに日本人は、一つまちがえば節操がまるで無くなる危うい国民といえましょう。
前回述べたように、自分さえ良ければ式の詐欺・偽造・捏造などは、今に始まったものではありませんし、またこれは手違いとかミスなどというものではなく、明らかに故意に行われた犯罪であります。そしてその組織のトップも、同僚も部下も、「みんなが黙っていれば大丈夫」という心算を共有して行われるたぐいのものです。その昔には、外国から経済的な利益のみを追求する日本人を評して「エコノミック・アニマル」と揶揄されましたが、いまだ汚名を返上した形跡はありません。
― 日本人は″節操の危うい国民″であることをしかと自覚すべし ― といった天の声が聞こえてきそうです。
アメリカの女性文化人類学者ルース・ベネディクトによって出版された『菊と刀』は、日本人と日本文化についての特質を論じた著作です。この書は、わが国の戦禍が治まらぬ昭和21年に刊行され、戦後日本の思想界に大きな波紋を投じました。
ベネディクトは、本書の中で日本文化の型を、欧米の「罪の文化」と対比して「恥の文化」だと断定しました。両者の違いは、行為に対する規範的規制の源泉が、内なる自己(良心)にあるか、それとも自己の外側(世評とか知人からの嘲笑)にあるかに基づいているとしています。
要するに欧米は、道徳の絶対的標準を説き、良心の啓発を頼みにする社会だから「罪の文化」をもち、他方日本の社会は、外面的強制力に基づいて善行を行うような「恥の文化」に属していると分析しています。「罪の文化」では、悪い行いがたとえ人に知られなくても自ら罪悪感にさいなまれますが、「恥の文化」では、人前で恥をかかないようにすることが道徳の原動力となるとしています。モラルの根拠が内にあるか外にあるかの違いで、言葉を変えれば「神との約束」と「世間様の目」の違いであると結論づけています。
たしかに、日本人の節操の危うさはこの辺にありそうです。日本人は、世間様の目がなかったら、あるいはみんなと一緒だったら、何でもやってしまいかねない無節操な面を持ち合わせている国民なのかもしれません。
昔も今も変わらぬ同じ「恥の文化」の土壌にありながら、武士が意識していた恥と、現在のわれわれが感じる恥がどこでどう違うのでしょう。
その手がかりが剣道にあると考えるものです。
(つづく)
*この『剣道みちしるべ』は、2007年8月〜2010年1月まで30回に渡り月刊「剣窓」に連載したものを再掲載しています。