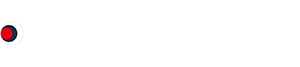図書
『令和版剣道百家箴』
「修養としての剣道を」
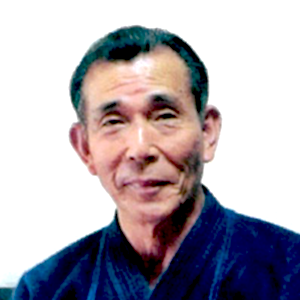
剣道範士 角 正武(福岡県)
「剣道百家葴」への寄稿依頼を受け、自身の修行の過程を回顧して伝統について稽えてみます。昭和18年12月に陸軍将校の息子として福岡に生を受け、戦後の混乱期に幼少年時代を送るのですが、腕白の仕放題で相当の悪童だったようです。昭和28年小学校4年生の折両親の勧めで護国少年剣道部に入門しました。
道場は福岡県護国神社の境内に、篤志家の奉仕によって旧家の解体廃材を再利用して建設されたものです。武道によって少年の健全育成を図ろうとする先達の願望の程が偲ばれます。時恰も剣道の組織的活動が7年ぶりに解禁されたばかりで、指導内容や方法は戦時武道への回帰は許されるものではなく、様々に模索の状態であったことと思われます。
指導の中心は礼儀作法の習得におかれ、基本動作や打込み、切り返しなどは先生の胸をかりて、伸びのびと稽古したものです。運動は器用ではなく巧みな動作は苦手でしたが、教えを忠実に守って先生に打ち懸かっていくと褒められるので根気強く稽古に通ったものです。同時期に小学校でも若い先生方(師範学校で剣道修錬を積んでいる)が、講堂の地下に秘かに保管されていた剣道具等を手づから補修して、男子の希望者に剣道の手解きを始めています。ここでも高圧的な指導はまったくなく、児童の意欲を引き出すことに重きを置かれていたと記憶しています。
寒稽古の皆勤を褒められたことや“剣道を習う者は決して粗暴に走ってはならない”という厳しい教訓が心に残っています。中学校では専門的指導を受ける機会に恵まれず、お互いに地稽古を楽しんだものです。中学3年生の折、知人の勧めで居合道に入門しました。古刀の真剣を譲り受けて週1回、英信流の稽古に通いました。
ある時好奇心から庭木の枝を試し切りしてその切れ味を実体験したことがあります。後日稽古の折に刀身に残った樹液の染みを先生に発見され、「破門にするぞ!刀は己れの邪念を切るものと心得なければならない!」と厳しく叱責されたことは忘れられません。15歳のこの時期に身につけた刀の扱い方や抜き付け・斬り込み・納刀の技術は、その後の竹刀打突剣道に活かされています。この時期に真剣に触れる体験を得たことをありがたく思い出しています。
高等学校の3年間は剣道の本筋を学んだ時期です。師範の松井 松次郎範士(当時80歳)は言葉で解説・指導なさることはありません。例えば、蹲踞から立ち上がってすぐに交刃の間に入ると、手を横に振って納刀してしまわれるのです。立ち上がったら先ず一歩退いて遠間を取り、身構え気構えをしっかり造ってから攻め入り捨て身の大技で打って出るという基本をしっかり教え込まれました。
大学2年生の折に、久留米市武徳殿に出稽古に行った際、“角くんの打ちには斬撃の風がある、そのまま伸ばしなさい”と励まされたことを思い出します。軍都と云われた久留米の高段者の稽古は実に厳しく、容赦無く突かれ体当りされて羽目板に飛ばされたものです。ところが嫌味の残ることはまったく無く、清々しく稽古を終えて師弟同行真剣味をもって渉り合うことの大切さを学ばせていただきました。
大学の後半には事業家の吉富 新師範にご指導いただくことになります。先生は松井 松次郎範士の剣道に憧憬を抱いておられ、大技で打込むことを推奨されました。“将来教師として剣道を指導する皆さんは、基本をしっかり身に付けなさい”と言われ、自らも真の基本を求めておられたのです。卒業まで一度も地稽古を頂戴することなく打込み・切り返しのみだった部員も少なくありません。私は時折地稽古を許され、機と見て思い切って面に打って出て手応えを感じても「角くん私の心は動いていないよ」と剣先が喉元にピタッと付いているのが常でした。気で攻め勝って相手の動いた処をすかさず打つという技の本筋に気付かせていただきました。
卒業の後は教職(高校・大学)に就いて多くの若者の指導に携わりましたが、勝負法の指導は苦手で専ら基本の修熟を促した覚えがあります。近年剣道修錬が競技志向に偏って、人間性の滋養が軽んじられている風潮が気掛かりでなりません。“勝ち負けは一瞬の戯れ、昇段は仮思めの証し、平素の稽古こそ生涯の糧”を提唱して修養としての稽古の継続を勧めています。心の錬り上げこそ大事と説いた先哲の教えを噛み締めたいものです。(受付日:令和6年7月26日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。