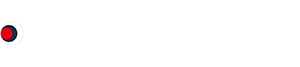図書
『令和版剣道百家箴』
「一刀両断」の攻撃的剣道で心を鍛える

剣道範士 鈴木 康功(兵庫県)
平成19年12月1日、東京九段会館において全日本剣道連盟主催の講演会が開催されました。講師は森島 健男範士で、テーマは「剣道再生への道」でした。森島先生の教えはそれまでにもたくさん受けていましたが、あらためて講話をお聞きし、大きな感銘を受け、今でも鮮明に覚えています。
日本剣道の本来の姿は攻撃的剣道ですが、全日本剣道連盟は昭和27年に発足した時に、これからの剣道は「体育的スポーツで行く」と宣言しました。そのため剣道は勝利主義に傾き、スポーツ的剣道になってしまいました。『究極のまもり』ともいわれ、左拳を頭上に上げ体を右一重にする防御姿勢である「三方守り」もこの延長線上で生まれました。流行の是正が叫ばれましたが、未だ直らないのが現代の剣道です。そもそも剣道は、打突部位を四か所に限定し、心理面を含めた優劣を競いあう競技であり、限定による心理的緊張の中でも不動心・平常心で打突を達成する真剣勝負なので、「三方守り」はふさわしくありません。攻撃的剣道にするためには、身を捨てて我が一刀にて敵をたおす「一刀両断」を一心に思い稽古しなければなりません。「一刀両断」が剣道の根本です。
上級者になれば、体力的・スピード的剣道を「心の剣道」に切り替えなければいけません。「心の剣道」とは、心に勝った印を技に表すことと言われています。いわゆる「初太刀一本」を逃がすなということになります。初太刀一本を工夫すると、無駄打ちや無理打ちがなくなる武道的剣道となり、打たねばならないとき、打ってはならないときを心得ることができます。これが我慢です。早く打とう・勝とうという剣道はスポーツ剣道であって、できるだけ早く卒業することが求められます。
武道的剣道は、打つ(切る)剣道をしなくてはなりません。相手と対峙し、気攻めして気が勝った時、自分の左拳を自分の口元まで上げ、右拳を額まで持って行って打つ。これが打つ(切る)剣道になるのです。この打つ(切る)剣道を稽古に稽古を重ねて自分のものとする。さらに応じ技のすり上げ・返し・打ち落とし技を習得する。すり上げ技は、面・小手を打突してくる相手の竹刀に対して、自分の竹刀の鎬で左右にすり上げて面・小手を打突する。すり上げる動作と打つ動作が一拍子になることが大切です。返し技は、相手が打ってきたことを感じると同時に体を捌き、受け返して打つ技です。面返し胴、面返し面、胴返し面、小手返し小手など多彩な技が使えることになります。打ち落とし技は、打突してくる相手の竹刀を左右に打ち落として、隙ができたところを直ちに打つ技です。面打ち落とし面、胴打ち落とし面、胴打ち落とし胴などがあります。
上級者は、この武道的剣道とすり上げ技等を体得し、日本剣道の本質を認識して後輩を指導すれば、「三方守り」の剣道がなくなり攻撃的剣道になっていくと考えられます。そして、日本剣道が素晴らしくなり、試合でも稽古でも、剣道の醍醐味が味わえるようになるのです。
最後に、私自身が実感した剣道のすばらしさを記します。令和3年の後半に喉の癌が見つかり、令和4年から放射線治療と4回の手術を受け、入院生活を送りました。毎回の手術の後には、リハビリの先生の検査がありましたが、歩行ができるか両手が上がるかなどの検査は毎回合格でした。それは剣道の稽古で培った精神力・根性・正しい稽古のお蔭だと考えています。私より若い入院患者に、腰が曲がり猫背になっている人がたくさんいました。猫背の人は認知症のリスクが高いそうです。剣道を稽古する人は頭が良くなり、有酸素運動によって痴呆症にならないといわれました。
退院して3か月以上は足がふらついて、ウォーキングも大変でしたが、令和6年4月末にはふらつきも治り、防具を付けて稽古を再開することができるようになりました。声帯の切除により、声を出すことはできませんが、心と気迫を高めることで稽古ができています。心と気は90歳でも100歳でも鍛えられるものだと思い始めました。ほかにも剣道で学べる良い点はいくらでもあります。剣道がますます盛んになることを切に願って筆を擱きます。
老いてなお 心・気鍛えて 励む道
(受付日:令和6年7月9日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。