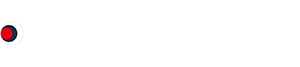図書
『令和版剣道百家箴』
「正念相続 兀々精進」

剣道範士 長内 淳介(青森県)
剣道にはその人の剣道観、性格、人間性が現れます。経験頼りに只相手を遣付けようと云う剣道では人間性を疑われます。
30代半ばの頃に武道書で「気剣体の働きに無理が有る。無駄が有ると云うことは運用が理に叶っていないと云うことであり、そこに虚隙を生じ相手に後れを取る結果となるばかりでなく疲労も早く身体故障の原因となる。又、相手構わず只打とう遣付けてやろうとするのは無法と云うものであり、欺いてでも勝とうとしたり相手を敬う心の無い不遜な振舞は心根が卑しいからである。そのような心では上達大成は望めない。心の持ち様を正し理に叶った稽古を積み重ねて初めて真の力を得るものであり心を養うのは日常である。道場ばかりが稽古ではない日常が修行だ」と云う鏡心明智流・桃井 春蔵(幕末期)の「三無の剣」の訓えを読み自分の剣道を考えるようになり、現在に剣道を続ける意味と自分の剣道に疑念を抱き、42才の時に大学時代の恩師・長崎 稔範士を御自宅に訪ね、御教導をお願いしました。「剣道は道であり自己を確立するための行である」と御教示戴き、改めて師事し先生がお亡くなりになられた平成9年まで月1回御指導戴きました。
御指導の中で「修行の過程」と「修行の心構え」について話され、「修行の過程」について、修行には段階が有り段階を経て本物が身に付くと芸道修行の「守破離」の訓えに依って「守は基本修錬の段階。基本の素振り、打ち込み、切り返し、掛り稽古、地稽古と学び体験を重ね努力して行く内に、気力・体力・技術と剣道に必要な様々なものが身に付いて来る。これが基礎作り土台作りの段階で一番大切な段階である。姿勢、構え、足捌き、気剣体一致の打突と正しい基本が身に付けば着実に向上する。破は発展充実の段階。身体能力の高さを生かして多彩な仕掛け技、応じ技と何処からでも打てる応じられる懸体一致の技術を身に付け駆使して色々な応じられる相手と稽古や試合をし、体験工夫を重ねて研鑽を積み、心技共に自分の個性に合った剣道に変革して行く段階である。離は自己確立の段階、意識的計らい無く相手に応じて自分を発揮する無心の働きに進展した段階である」と。「修行の心構え」については、修行に終りは無い、教えを受け入れる素直さと自分の剣道を求める熱意を失わず、常に前向きに工夫して稽古を積み重ねることであると柳生流「三磨の位」の「習工錬」の訓え「習とは師事伝習、良い師について正しい指導を受けること。工とは正念相続、師の教えを聞き放し習い放しにしないで自分のものとするよう工夫すること。錬とは勇猛精進、習い工夫したことを体得するために一心に稽古すること」を教示されました。これ等の御教示を得て、私の剣道に対する思いが定まりました。
稽古や試合で相手を打った、相手に勝った過去の経験に捉われて打とう勝とうと技の速さや手数と云った身体能力に頼った剣道、変則的動きで眩惑して打つ等の剣道は身体能力が高い30代までは通用しますが、身体能力が衰えるに連れ、通用しなくなると共に個癖が強くなり、剣道も崩れてしまいます。基本がしっかり身に付いて理合に叶った稽古をしていれば崩れません。年齢による身体能力の衰えも基本の素振り、打ち込み、切り返し、基本技と基本稽古を通じて現在の自分の身体能力を確かめ調整していれば解決出来ます。身体能力の衰えを気で補い、技を絞って、無理打ちをしない気と理合の剣道に変革して行くのです。何時までも同じ剣道では通用しなくなりますし出来なくなります。年齢に応じた剣道に変革して行くことが必要です。
構えと打突の基本をしっかり身に付けた上で、身体能力が高い30代までは身体能力を生かして、多彩な技を駆使した気剣体一致の剣道を心掛け、身体能力が衰えて来る40代からは身体の動きに頼らない気の剣道に徐々に変革し、50代からは極力技を絞り気と理合の剣道、心気力一致の剣道を心掛けて行くことです。そして最終的には、気で相手を制す境地を目指すのが理想的であると思っております。
剣道の力は地道な努力の積み重によって培われ備わります。「正念相続 兀々精進」剣道は生涯を通しての自己修養の道です。(受付日:令和6年6月24日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。