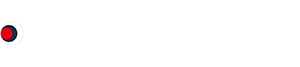図書
『令和版剣道百家箴』
「先達に学ぶ」
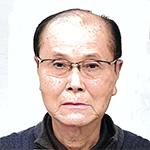
剣道範士 中里 誠(茨城県)
昭和38年盛夏、講談社野間道場の朝稽古は、激しい息遣いと張り詰めた緊張感が漂う連日でした。こうした中で巡り合わせた持田 盛二先生の一言。「修行者は『はんすう力』を磨きなさい。」は、その後の人間形成を図る上で、大きな影響力を及ぼすこととなりました。
所詮浅学の身、この言葉の本意を咀嚼するすべもなく時が過ぎ、後年、小川 忠太郎先生再三、ご来県の折「独妙剣」のご高説の中から「反芻力」の奥深さ(思考の深化)を拝聴し、さきの野間道場での持田先生の至言と重複させ、新たな決意を固めたことが想い出されます。
このように、今に息づく先達の実践哲学を武道文化として考察することは、単に修行の本質に立ち返るだけでなく、膠着した意識、感覚を払拭して新たな世界を展望するために、大きな意義があると考えます。
もとより、剣道再興の先駆的役割を果たしてきた先達の足跡を紐解くと、いかに卓越した先見性と行動力、強固な使命感と情熱は命懸けで自らを成長させ、人の心に高邁な精神を刻み続けてきたか。信念を貫いた心奥には、剣道文化の根源である「真剣の本質」を思想的基盤とした気高い矜持(自負心)が、確固たる修行観として確立されていたからだと思われます。
このように、意識の高揚を図りながら、それぞれの時代に魂を込めて生き抜いてきた先達の信条や、遺された語録には多くの叡知と教訓が凝縮され「不易流行」として実践を促しているはずです。「先達に学ぶ」という真意もここに込められているわけで、私達は今こそ伝統文化の重みを再認識して、正しい剣道文化の普及に寄与する使命があるのです。
現在、剣道は形(現象面)だけの傾向が強くなり、その本質がスポーツ化されてしまっているのです。その結果、剣道の根源としての術技は、表面上のものとなり、虚実や気の伴った対人活動が希薄となったような気がします。
本来修行のあり方は「初年は技を習い、中年には気を錬り、後年には位を学ぶ」と言われてきましたが、この原点を見失った時その道は、必然的に自滅の方向に向かい、気づいた時は手遅れとなり、元に戻れません。
私達は、この時代を越えても不変の真理である原点を、真の剣道文化として融合させ、時代の変化や流れに活かすことができますし、活かしてこそ普遍的価値の尊さを世に問うことができるのです。
「あの教え、学びは何だったのだ」ー「答え」はいつも目の前にあるのです。見えていないのは、「問い方」にあるのです。私達は、この素朴な問いかけや気づき(見とり、聞きとり、読みとり)から己の心中を刺激して、本質や深さを追求していくという鋭い自己観察(内観)能力や思考力を磨いて行けば、道は自ずと開かれます。
大切なのは、修行の要諦「三磨の位」(習・錬・工)から身につけた実践論に、内観から生じた心証を問いかけて「事理一致」の大義に整合しているか。根気よく検証(反芻)を繰返す謙虚さが、己の存在感を高めます。
修行は単なる精神論ではありません。活人剣としての調和融合や気の世界。気が出る(伝わる)ような自分に進歩成長しなければなりません。この進歩成長は、変化し、深さを悟ることであります。稽古の本質(温故知新)もここにあるはずです。
「自分は今まで何をしてきたのだろう」という自覚こそ変化であり成長です。そうした気づきは常に未来を拓き、豊かな心を育みます。また心が開放されているので内なる気が出てきて自分を明るく大きくしてくれます。この気づきを与えてくれる最高峰のひとつが先達が築いてきた形(型)稽古と、それが遣える師(先達)の存在です。
自分に知らないということを、素直に知ったときにはじめて「伸びている」「成長した」と言えるのです。知らないのに知っているとの思い込みは、最大の居づき(思考停止)です。大切なのは、知識の量や速さではなく器(胆力)を大きくすることです。
まさに、先達が遺した実践哲学は、私達が未来を創造する貴重な財産(宝庫)であり、活動指針となることを共通認識とすることが、剣道文化の本質を身近なものとして、次世代に繋ぐ最大の修錬課題といえるでしょう。(受付日:令和6年7月8日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。