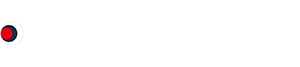図書
『令和版剣道百家箴』
「百不当の一老」

剣道範士 島野 大洋(大阪府)
「失敗は成功のもと」というが、けだし、成功の一当は失敗という百不当の一老(蓄積)によるものである。
道元禅師が修行に励む学僧に譬えとして語った教えである。(『正法眼蔵』)説心説性の巻)。弓で的を射るが、一向に当たらない(百不当)。しかし、その当たらない矢を何本も何本も放って修練に修練を積むと、その修練の力によってやがて当るようになる。その金的を射ぬいた一当は、それまでの百不当の力であり、百不当の一老(蓄積)である。それと同じで、どんなに努力しても、はじめのうちは百行に一当なしで、さっぱり証契するところがない。しかし、先達に導かれ、書籍に親しんで実践を積み上げると、それまでの百不当の力によって一当を得るに至るのである。
少年時代、剣道との出会い
昭和20年(1945)8月15日、私が6歳の時、大阪府岸和田市岸城町で終戦を迎えた。
私が剣道を始めたのは、昭和29年(1954)春、15歳(中学3年)の時である。戦前、大阪府警で剣道教師をしていた父(明治44年生)に最初の手解を受けた。戦後、昭和27年3月に全国に先駆けて大阪府剣道連盟が創立されて2年ほどしか経っていない頃であった。道場(大阪府立岸和田高校体育館)は大人ばかりで中学生は私一人であった。父の持論は「剣道は基本をしっかり身につけないと上達しない」というもので、踏み込んで打つ動作が手足が合わず、出来るまで絶対に防具を着けさせてくれなかった。今にして思えば、父の指導に深いありがたみを覚える。
高校時代、初めての坐禅
昭和30年(1955)大阪府立佐野工業高校(機械科)に入学。当時、泉州の高校で唯一剣道部があったので早速入部した。部活顧問は中村 二郎先生(六段)で部員は13名位だったと思う。戦歴は3年間を通じ、団体戦は2回戦進出が1回だけと振るわなかった。私が3年の時、大阪高校総体、個人の部で3位入賞が唯一の戦歴である。高校2年(二段)の夏、中村先生から、夏休みを利用して、奈良県にある寺に1週間の予定で合宿しないかとお誘いを受け先輩(3年)一人を加え同行した。合宿先は、曹洞宗「慶田寺」で御住職は、大竹智光師。境内に道場があり、午前午後が稽古、夜は坐禅の日課であった。大竹師は、容姿端正で剣道も立派で、午後の稽古でご指導を受けた。坐禅は、午後9時より本堂で、本尊を背に大竹師が座り3人は、師と対面し坐禅の心得等を学び、約1時間の坐禅であったと思う。その時、初めて習ったお経が「般若心経」で師が一節を朗々たる美声で読経され、3人が唱和する形で、1週間後には暗唱できる迄になっていた。6日目の坐禅で厳粛な雰囲気と静寂の中で頭が冴える不思議な心境を体験した。
大阪府警察剣道指導者への道程
昭和33年4月(1958) 大阪府警察官を拝命。昭和34年4月、大阪城内にある機動隊に配属。昭和35年4月(1960) 待望の剣道特別練習生 (特練) となる。
当時の本部師範は、主任師範・越川 秀之介範士九段を筆頭に、指宿 鉄盛・斉藤 正利・長谷川 寿・土田 博吉・六反田 俊雄・坂本 吉郎・小林 嶺造・岸本 政一と錚々たる先生方であった。特練生は、教士七段の先輩方と五段〜参段の若手22名で、有望な新人が採用されると入れ替えられる厳しいものであった。指導は、基本を重視し、試合、地稽古、掛り稽古と連日激しく厳しいもので、百錬自得の稽古であった。
私は31歳 (七段) の時、右肩腱板を痛め、特練を外れ、警察署の剣道教師に転出した。その後、本部剣道主席師範、術科指導室長を最後に退職。 今年剣道一路の人生70年を迎え、生涯修行の剣道を楽しんでいいのではないかと思う昨今である。
私から伝えたい事
「打って反省、打たれて感謝」
剣道におけるあらゆる技術は、瞬間に生れ、瞬間に消える。いわば、瞬間的な芸術である。この芸術は、自らの反省、工夫によって独創されるものであり、創造されるべきものである。しかし、それは絶えざる工夫と努力、即ち、稽古が伴って立派なものができるのである。いかに器用な人といえども努力のない人は稽古の数をかけた努力の人には及び得ないものである。剣道上達の秘訣は、反省、工夫、研究と共に、一本でも多くの数をかけた稽古が第一である。(受付日:令和6年7月26日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。