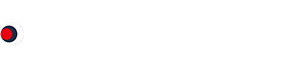図 書
剣道と「き」
第6回 江戸時代後期の武芸気論
全剣連 広報・資料小委員会 委員
埼玉大学 名誉教授
大保木 輝雄
1.「かた」の変容
近世において武芸を学ぶことは、「かた」を「習う」ことでした。兵法家伝書には「習をわすれ、心をすてきって一向に我もしらずしてかなう所が道の至極也、此一段は、習より入りて習なきに至る者なり」とあります。つまり、「習」を離れ「かた」そのものに成り切ったとき、自由で創造的な技(事・業)を手中におさめることができ流祖の「すがた」が自分の身体に現れ出てくることになる、というのです。このあたりの消息は、山岡鉄舟(1836〜1888)にも見ることができ、鉄舟は「一刀流兵法箇条目録」の中で「一刀齋のまねをして、くせを覚ゆるの心なり」と述べています。
しかし、代々受け継がれていくはずの「くせの勢」は、だんだん形骸化の一途を辿ることになります。その背景には、戦時体制から平和体制へと社会事情の変化に伴い、人々の精神的緊迫感が変質してしまったことや、技術の伝承や上達とその技術を何時でも何処でも使えることとは自ずから次元が違うという「かた」そのものがもつ限界性にありました。
時代の激変が予兆される江戸時代後期になると、「かた」稽古を補完する意味で防具使用の竹刀打ち込み試合稽古方式(撃剣)が考案され、同時に道教的「練気養心」論も論議されるようになりました。その流れは、流祖の「くせの勢」を獲得するために、いかに虚構勝負空間を緊迫したものに作り上げるかといった工夫の歴史と言ってもよいでしょう。流祖の獲得していた何ごとをするにも自由な心の位を追い求めたのです。鉄舟は「全ク敵ニ上手下手アルニアラズ。自己上手下手ヲツクレル事確然タリ。自己アレバ敵アリ、自己ナケレバ敵ナシ」と述懐し、自分の身体に心のありかを問うたといっています。「かた」のもつ本来の意味は、自己の身体を問うことを介在させてのみ会得できるのでしょう。
2.白隠の「練丹の法」
19世紀初頭、鉄舟より一世代前の剣客白井 亨(1783〜1843)は次のように述べています。「昔年、針ヶ谷夕雲、小田切一雲、金子夢幻、山内蓮心等ノ遺書アリ。各、兵法ニ於テ微妙ヲ得テ其所得ヲ述タルハ天下人ナキガ如シトイヘドモ、其書真理ニ通ズトイヘドモ、練丹ノ法ナクシテ階梯ナキガ故ニ、空理ニ均シ」(『兵法未知志留辺』)。もとより兵法の精妙の境は自得以外にないのですが、白井は、そのような天才的な武芸家のみが獲得できた境地を、白隠(1685〜1768)の提唱した練丹の法を学び、初めて体認できたと述懐しています。「練丹の法」を学ぶことによって、誰でもが先達の心の位(精妙の境)を会得できると言っているのです。
白隠は練丹の法について次のように述べています。形を錬るの要、神気をして丹田気海の間に凝らさしむるにあり。神凝る則は気聚る。気聚る則は即ち真丹成る。丹成る則は形固し。形固き則は神全し。神全き則は寿がし」(『夜船閑話』)。意識や呼吸を臍下丹田に集中して気をそこに集めると、丹田のあたりが固くなる。そうすれば気力体力が充実し「元気」という状態が獲得できるというのです。このことは、中国道家の系譜にある心身訓練法が武芸に導入されたことを意味します。つまり、イメージや呼吸を介して心身統一のようなものが実践されていたのです。いずれにしろ、自己の心身の働きは「気」の感覚を媒介として説明されます。
3.「かた」と撃剣
北辰一刀流では「組を以て本とし試合を百練して活変の法をさとり、息合いを強くし、手足一身の働きを自在にして後又其心気形刀一致、無念必勝の妙処に至りては、又組を以て習熟し明悟するに至らんと欲するなり」と述べ、「かた」は、初心者の学ぶべき基本であると同時に、いわゆる極意であるといった二重の意味をもつと伝えています。「かた」は、流祖の切り開いた境地の身体運動的表現であると同時に、技術指導の指針でもありました。それゆえ、「かた」のもつ二重性を繋ぐものとして、その本来の意味を会得するためには、防具着用の試合稽古(撃剣)や練丹の法等による新たな身体訓練法の導入が必要だったのでしょう。
このような流れを見てくると、流祖の身体を共有することは、「き」を介在させて自己の身体を組み替えることだと言えそうです。
(つづく)
*この『剣道と「き」』は、2004年9月〜2005年9月まで12回に渡り月刊「剣窓」に連載したものを再掲載しています。