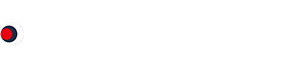図 書
剣道と「き」
第7回 江戸時代後期の武芸気論―2
全剣連 広報・資料小委員会 委員
埼玉大学 名誉教授
大保木 輝雄
1.実体としての「気」
幕末に活躍した窪田清音(1791~1866)は、「形」と竹刀打込試合を融合させた剣術論を展開し、その実践を反映した多くの著作を遺しています。旗本であり講武所頭取兼兵学師範役ともなった清音の「気」論は、以前に述べた近世初期・中期の武芸伝書にみられる「気」の用例がいわば概念としてのニュアンスが強いことに比して、身体の内部感覚や意識に即した実体として扱われているところに特徴があります。
清音の著作である『剣法初学記』『見聞集』『剣法梯伝授』などには、「心気理の研究は初学に益なし業を習ふの数多きに如かず、其業未だ熟せずして理気の工夫を専らすれば迷ひを生じて熟達し難し」、「業を励むは鏡を磨くが如く、鏡は心なり、業に随ひて心明らかなり」とあり、さらに「人必ず自ら足らざる所を知る。自ら足らざる所を知れば、業も気も心も共に進みて益々上達すべきなり」という記述が見られます。剣術のみならず柔術も修め、武術全般に精通していた清音は、「気」と「業」=技の関係性を洞察し、「かた」や「試合」の実践を通して、何よりもまず技の修練に努めよ、と述べているのです。
『剣法初学記』にはまた、「気と共に太刀を運らす」「足は気に後れざるを要とす」「手の締りは小指の先に少しく気を用い」とあり、「気」が体験によって開示される身体性に即した具体的な感覚を指し示す言葉としても使われています。
2.内―外の「あいだ」にあるもの
剣の道を学ぼうとする人の為の道しるべとして書かれた『つるぎの枝折』で、清音は心と気の関係に関し、簡潔明瞭に述べています。「心は躰、気は用(=はたらき)也。心より気へ継ぎて用をなす。躰は内にして用は外なり。心気正しからざれば、外用を全せず。心を明にして其情術にあらはるるにあらざれば剣法ととのわず」「業は気の働きを本とする。気より眼目へうつり、躰にも手足にもわたり、相共にひとしく働かざれば、其わざ全くととのはず。其わざととのひたるを名付けて術といふ。気、目、躰、手、足、五つともに遅速なく、其程をはづれざるときは、自在のはたらきなるべし。かくのごとくなれば、此の術全く己がものとなる也。己がものとならざれば、まことの勝は得がたし、又其気目躰手足の五つのもとは心也」。内にある心のはたらきや動きは「情」として具現化され、それが身体の表情として外に現出し、相手への影響力として伝わる。清音は、自己の内―外の「あいだ」を往来する実体を「気」と見なしているのです。
3.自―他の「あいだ」にあるもの
さらに立逢ば場間のはからひに心をくばり行末を見て立あいかまえて備ふべし」といった敵対空間を前提として、「彼が心と気とを見るべし」「常に心を鎮め気を下し学ぶ時は、次第に曇りなきに至り、気のおこる所をのつから<おのづから、筆者注>もとめずして知る妙なる位に至る」と述べ、「気」の存在を、立ち合い場面に即した相手と自分、自分の心と身体との間に実感される実体として捉えました。「いまだ勝負わからざる内、かまえを中段又は下段に備、いかにも堅固にして気を押さえ、次第に場合をつめ進まざいかがせん」といった状況のなかで「居つき居つかざるは心気のめぐりにあること也」「生涯の勝を取は、心気と法術とにあり」と言及し、相手を観察する心が自分の内部で働いている気に悪影響を及ぼさないよう、「心気」の鍛錬と身体技法が重要であると強調しているのです。清音はまた姿勢と「気」の問題との関連にも言及し、「かた」や「しあい」の実践を、「あしのふみかた広からずせまからず、心気納まり、臍下にみちて腹を出し、腰のつがい正しく胸をはり、肩落、頭のすはり正しく、いずれの所といへどもたらざる所なし」といった理想的な身体と心の「備え」を獲得して「気の充実」が達成できれば、自分の力を自由自在に発揮できると述べています。
以上のような清音の「気」論からは、近世初期に気の心法論として提起された武芸心法論が、中期に論理化され、激動の時代となった後期に至って実践期を迎えたことが読み取れるのです。
(つづく)
*この『剣道と「き」』は、2004年9月〜2005年9月まで12回に渡り月刊「剣窓」に連載したものを再掲載しています。