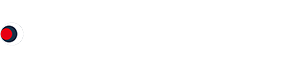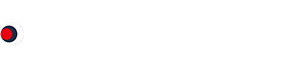図書
広報・資料小委員会コラム
第3回 「豊臣秀次の切腹事件と刀・脇指」
委員 矢部 健太郎
1 広報・資料小委員会との関わり
私が当委員会に関わるようになったきっかけは、國學院大學剣道部の先輩であり、文学部教授でもあった加藤寛氏にお誘いを受けたことでした。幹事として書記を務めた記録を遡れば、その始めは2003年11月でしたので、もう20年近くになります。この間、『鈴鹿家文書』解説の執筆に関わることなどもありましたが、剣道史・武道史等を専門とされる先生方の中にあって、日本史学、特に戦国・織豊期の研究を続けてきた身としては、門外漢という感を禁じ得ません。しかしながら、むしろそれ故にこそ、委員会の場では常に刺激的な学問的示唆を受けられるということもあり、個人的にはたいへんありがたく思っております。今回のコラム執筆に際しても、少々毛色の異なる話になることをご容赦いただければ幸いです。
先に私の専門領域を戦国・織豊期としましたが、さらに絞れば豊臣政権の研究、豊臣期の公武関係や大名支配秩序ということになります。平民から史上初の「武家関白」まで駆け上った羽柴秀吉は、日本史上稀にみる立身出世を体現した者であり、好きな歴史人物ランキングの常連といえるでしょう。ただし、天下一統までの過程と比較すると、彼の晩年に対する評価は著しく低くなってきます。朝鮮出兵や二代目関白・豊臣秀次の切腹事件、サン=フェリペ号事件にともなう二十六聖人殉教事件など、血なまぐさい事件が相次いだことにより、「秀吉は耄碌した」「幼い秀頼を残し、政治的混乱を終息させることができずに亡くなった」という理解が一般に浸透しているのです。
そうした通説的理解に対して、私はいくつかの観点から見直しを図り、これまでに、博士学位申請論文をもとにした『豊臣政権の支配秩序と朝廷』(吉川弘文館、2011)、豊臣政権の構造的特質から新たな関ヶ原合戦論を打ち出そうとした『関ヶ原合戦と石田三成』(吉川弘文館、2014)、そして『関白秀次の切腹』(KADOKAWA、2016)という単著を世に出してきました。
2 秀次の切腹と「刀」「脇指」
『関白秀次の切腹』では、秀吉晩年の蛮行とされる「秀次切腹事件」をはじめとする一連の事件に関する史料を再検討し、「秀吉に秀次を切腹させる意思はなかった」という結論を導き出しました。ちょうどNHK大河ドラマ「真田丸」が放映されていた年の4月に刊行されたこともあり、脚本の三谷幸喜氏にもお読みいただけたようで、7月放映の「秀次事件」を巡る回では、「秀吉の命令による死刑」という通説とは異なり、「秀次自らが死を選ぶ」という斬新な描き方がなされ、さまざまな反響がありました。
もちろん、秀次が切腹したことは歴史的な事実です。織田信長の一代記『信長公記』の著者・太田牛一による『大かうさまくんきのうち(太閤様軍記之内』)には、秀次切腹の場面、そして、その介錯をおこなった篠辺淡路守について、以下のように記されています。
五番、関白秀次卿、御わきさしはまさむねにて、御かたななみおよぎ、さくかねみつ、さゝべあわぢのかみ御かいしやくつかまつり候て、そのゝち、ぬしも御わきさし国次をくたされ、はらをつかまつり候、
篠辺淡路守は、天下一の茶人・千利休の切腹を見届けた人物ともされています。月日がめぐって、関白秀次の介錯役を勤めた直後に殉死するという、なんとも壮絶な人生を送りました。ちなみに『大かうさまくんきのうち』では、秀次および殉死した者たちの顔ぶれとともに、使用した刀剣類の名も書き残されています。
一番 山本主殿 脇差・国吉
二番 山田三十郎 脇差・厚藤四郎
三番 不破万作 脇差・鎬藤四郎
四番 龍青西当 御剣・村雲
五番 秀次 脇差・正宗
六番 篠辺淡路守 脇差・国次
いずれも名だたる名刀であり、刀剣類の「目利き」であったという秀次の教養や権勢をうかがい知ることができるでしょう。
ところで、私が「秀次事件」の見直しを行う必要性を感じた背景には、豊臣宗家にとって最大の強みである「摂関家」という家格の象徴である「関白」に、果たして切腹を命じるのだろうか、という単純な疑問がありました。そこで関連史料を見直した結果、『太閤記』にのみ残る石田三成ら「五奉行」連署の「秀次切腹命令」は、実は著者・小瀬甫庵による偽作であることがわかりました。そして、その前日の「秀次高野住山令」によれば、秀吉が秀次に命じたのは「死刑」ではなく「禁固刑」であった、との結論に達したのです。
『南行雑録』(東京大学史料編纂所写本)に残るその法令の第一条には、「一、召仕候者、侍十人此内坊主・①台所人共、下人・小者・下男共五人、都合拾五人タルヘシ、此外小者一切不レ可レ有レ之、然者、②ホツタイ黒衣之上ハ、上下共刀・脇指不レ可レ帯之事、」と記されています。現代語に訳せば、「一、召し使うことのできる者は、侍十人[この内に坊主・台所人を含む]、下人・小物・下男五人を加え、十五人とする。この他に小者を召し仕うことは一切禁止する。ただし、出家の身となり黒い袈裟を着ている以上は、身分の上下にかかわらず、刀・脇指を携帯してはならない。」ということになります。
傍線部①の「台所人共」とは、いわゆる「料理人」のことです。秀吉が秀次に料理人の供を許したのは、秀次がこの先も高野山で長く生活していくことを前提にしていたからと考えられます。すなわち秀吉は、この法令が届いた翌日に秀次が切腹することなど、まったく想定していなかったのです。
同時に傍線部②では、出家した以上は刀・脇指を携帯してはならない、と述べています。刀・脇指といえば、武士の身分的象徴であるとともに、戦闘や切腹の際に使うのが一般的です。切腹について述べれば、腹を切るのに刀は長すぎるので「脇指」を用いますが、それだけではただちに絶命するわけではないので、早く苦しみを取り除くため、介錯人が首を切り落とす時に「刀」を使います。すなわち、秀吉がすでに出家の身となった秀次から刀・脇指を取り上げた意味は、自死行為の予防策であったということになります。現在の刑務所において、収監される者の身体検査が行われることと共通する考え方です。
こうしてみてくると、秀吉が命じたのは「高野住山」=「禁固刑」であって、「切腹」=「死刑」ではなかったことがわかります。それでも、秀次が切腹したことは歴史的事実です。そうなると、秀次は秀吉の命令によってではなく、自らの意志によって腹を切った、ということになるのです。その評価の転換は、単に秀吉や秀次という個人の人格・関係性のみならず、秀吉晩年の大局的な政治情勢についても、大幅な見直しを迫るものといえるでしょう。
3 中世と近世の違い―「殺人剣」から「活人剣」へ―
中学・高等学校の歴史教科書などでは、織田・豊臣政権期を一つの画期として、室町幕府までを「中世」、それ以降を「近世」と呼んでいます。とりわけ、信長の「楽市楽座」、秀吉の「検地」や「刀狩」といった政策により「兵農分離」が進んだことが、中世と近世の決定的な違いであるとされてきました。しかしながら、「楽市楽座」は信長のオリジナルな政策ではなく、秀吉の「検地」も「刀狩」も、全国的に行われたわけではありません。彼らの政策は、確かに「近世を志向していた」けれども、完全に中世を脱却できたとは言いがたいのです。
むしろ、政治的な争いがどのように解決されてきたか、という視点に立つと、別の見方も可能になります。「剣豪将軍」足利義輝が暗殺され、本能寺の変で織田信長が、大坂の陣で豊臣秀頼が命を落とした時代。当時は、刀剣が武器として実際に人の体を傷つける時代でした。そうした政治的な争いが、ようやく裁判などによって治められるようになり、刀剣が人の血を吸うような時代は終わり、武士の「身分標識」となっていくわけです。それはまさに、「腹が減っては戦はできぬ」という時代から、「武士は食わねど高楊枝」という時代への劇的な変化といえるでしょう。剣道の世界でいわれる「殺人剣」から「活人剣」への転換は、やはり江戸幕府による確固たる全国支配体制確立が不可欠だったのであり、これこそが「中世」と「近世」との大きな違いといえるのではないでしょうか。