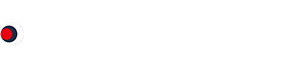図 書
剣道技術の成り立ち
第2回「踏み込み足」の形成過程(2)
全剣連 広報・資料小委員会 委員長
明治大学 国際日本学部 教授
長尾 進
踏み込み足を剣道技術の一つとして位置づけ、それに伴う余勢も容認する著述が大正時代に一部であったことは、当時すでに剣道の実践場面において踏み込み足とそれに伴う余勢が多く出現し、そのことに対する理論付けが必要となっていたことを意味しています。では、そもそも余勢を伴うような踏み込んで打つ技術はいつ頃から出てきたのでしょうか。少し遠回りになりますが、剣道具(防具)を使用した剣術の発展過程を最初に見ておきたいと思います。
史料のうえからは、1660年代頃には「皮具足」や「面顋(めんあご)」と呼ばれる道具を着用して稽古をする流派があったことが、明らかになっています(中村民雄氏「剣道具と道場の発達」、『剣道の歴史』参照)。その後関東においては、正徳年間(1711~16)の直心影流における道具の改良や、宝暦年間(1751~64)の一刀流中西派におけるその採用などを契機として、剣道具(主に面と小手)を使用して稽古や試合を行う流派が増え、1700年代末までには、全国的に行われるようになりました。
ただし、この頃までの剣術について堀正平著『大日本剣道史』(1934)では、「1メートル(三尺三寸)内外の撓(袋竹刀)を持って、進退は常の歩行の如く(今日の形と同じ)した。即ち右左右、又は左右と進んで切るのが普通であった」としています。
その後、筑後柳河(柳川)藩士で剣術と槍術の師範であった大石進が、天保年間における二度の江戸在勤(1833年と1839年)中、五尺三寸の長竹刀を駆使して江戸中の道場を席巻します。そのことを契機として長竹刀が急激に普及しますが、「柄が八寸以内の竹刀の時は、常に歩む通りで宜かったが、長竹刀に変ると柄も随って長く一尺三寸許りにもなったので、歩んだのでは構えが動揺する、夫れを動かすまいとすれば窮屈であるから、形のように歩んだのを止めて、右左と順に足を運ぶ様に変った。今日の足遣ひは、この時からで昔の足遣ひに比して板間で早い事をするには便利であるが、地面に於ては、ハヅミが出ぬから沢山は進み悪い」と、剣術において「送り足」が多用されるようになり、「板間での剣術」すなわち竹刀剣術独自の足さばきが生成したことに、堀範士は言及しています。
残念ながら堀範士はこれらの記述の論拠となる出典を明記されていませんが、大石を破ったという逸話の遺る男谷精一郎(直心影流)も『武術雑話』のなかで、「近年稽古に用ひ候竹刀長寸に相なり、其うへ先きをいかにも細くいたし、長きは鍔先き三尺六七寸、柄共に五尺余のしなへを用ゆる人多し。稽古の勝口には寸長き利多し。―中略―。是、実事と甚敷懸隔致し候ことにて、真剣にては目方も重く、中々竹刀の所作の如く双手の突撃共に相成り申さず」と述べていますように、長竹刀の流行が、従来の剣術とは違った竹刀剣術独自の技術形成の一因となったことは明らかなようです(榎本鐘司氏「幕末剣道における二重的性格の形成過程」、『日本武道学研究』参照)。
天保期には、老中を務めた水野忠邦が文武奨励の立場からそれまでの他流試合の禁を緩めたことから、同期以降他流試合が表立って行われるようになりました(大石の他流試合もこのことが背景にあります)。各藩の江戸藩邸においても御前試合が行われるようになりますが、嘉永4年(1851)に藤堂藩江戸藩邸で行われた試合の様子を、久留米藩士・武藤為吉が師である加藤田平八郎(加藤田神陰流)に送った書簡の中に、千葉周作(北辰一刀流)の次男・栄次郎の剣術を評した部分があります。「上段・中段・下段何とも上達、なかんずく、誓願にて真に試合の節は、踏込で撃突致候。其神速成事、中(あたり)と云、気前と申、実に一点の申分御座なく」とあり、「踏込」を伴う迅速な技を繰り出していたことがみてとれます(村山勤治氏「鈴鹿家蔵・加藤田伝書『剣道比試記』について」参照)。また、弘化年間から嘉永年間にかけて千葉周作の門に学んだ高坂昌孝(姫路藩)が遺した『千葉周作先生直伝剣術名人法』にも、「踏み込み」や「飛び込み」という記述が多くみられます。幕末の北辰一刀流では、技に迅速を得るために「踏み込む」ことや「飛び込む」ことが認められていました。
(つづく)
*この『剣道技術の成り立ち』は、2005年10月〜2006年3月まで6回に渡り月刊「剣窓」に連載したものを再掲載しています。