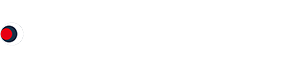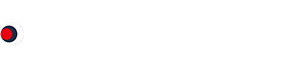図 書
剣道技術の成り立ち
第5回 竹刀剣術の技術形成と体系化
全剣連 広報・資料小委員会 委員長
明治大学 国際日本学部 教授
長尾 進
前号では、剣道における面技重視の技術観が、近世後期に生れてきたことについて述べました。一方で近世後期には、竹刀剣術独自の技術研究や体系化も急速に進みました。前記したように、剣道具(防具)を使用しての剣術稽古は1600年代半ばまで遡ることができますが、それは各流派における修練上の必要(安全面への配慮など)に応じた簡素な剣道具を使用してのものでした。その後、1700年代後半からは、広範囲な廻国修行や他流試合を行う者も一部には出てきましたが、剣道具や剣道技術についての交流や情報交換が飛躍的に進んだのは、他流試合の禁が解かれた天保期(1830~1844)以降のことでした。
天保期に水戸藩の郷校の剣術師範を務めた、助川郷(現日立市)の郷士・武藤七之介が書き遺した『神道無念流剣術心得書』には、神道無念流の立場からみた一刀流(中西派)、直心影流、鏡新明智流、柳剛流、新陰流(肥後)、義経流、浅山一伝流の技術的特徴、およびその対処法が克明に記されています。たとえば一刀流は、「竹刀を下段にもち、此方の胸板より面へかけてつき(突き)、左右の小手を打、胴を打つ」という特徴があるので、これに対しては、「敵より先へ打ちを出し、小手より面へしげくうつべし。敵のつき後になり、此方先になる」、あるいは「必立合て、つき有と思ふべからず。つきもうちも皆一様のものなり。つきありと思へば、此方身体乱て必まくべし」という対処法(心得)が記されています。
また、鏡新明智流については「左りの足を先へ出し上段に取。上段より此方の面・小手をうつ。其上段のすみやかなる事、電光の如し」という特徴が記されています。この左上段からの素早い打撃に対しては、「間遠きに敵の上段此方の頭へ来る節は、しかとうけとめ敵の左脇下へうちこむべし」、あるいは「右の小手へ来る時は、さしとめにて敵の右の小手より頭へかけてうつべし」とあります。
これらは、今日の剣道においてもそのまま通じるような技術や心構えであり、現代剣道の技術的ルーツはこの時期に芽生えたものと思われます。
同書にはこの他にも、この頃までの胴(竹具足)が身体運動の自由を妨げる構造で、組打には不向きであったこと。また、胴を使用しない流派と立ち合うときには、こちら(神道無念流)も胴を使用しないことや、柳剛流のように足(脚)も含めて「五尺の体をきらひなく」打ってくる相手には、こちらも「敵の五尺の体の隙を見て」打ってよい、というように相手との関係において公平性を保とうとする考え方があったことなど、興味深い記述を多く見出すことができます(『剣道の歴史』資料編所収)。
さて、時代が進んで弘化・嘉永期になると、さらに竹刀剣術の技術は整備され、体系化されて行きます。千葉周作の門に弘化期から嘉永期にかけて学んだ高坂昌孝(姫路藩)が、周作の校閲を得て北辰一刀流の竹刀打ち技術を分類整理したのが、いわゆる「剣術六十八手」(『千葉周作先生直伝剣術名人法』所収)です。「剣術六十八手」は、面業二十手、突業十八手、籠手業十二手、胴業七手、続業十一手から構成されていますが、個々の技は今日の剣道においても有効と思われるものが多く(なかには、全く行われなくなった技術もありますが)、その後の剣道技術の基盤ともなりました。また、一刀流の組太刀(形)が応じ技中心であるのに対し、剣術六十八手はしかけ技が多く、加えて組太刀にはない片手技も十手含まれていることから、従来の形剣術とは一線を画した竹刀剣術独自の技術体系であったことが、小林義雄氏らの研究で明らかにされています。
前出『神道無念流剣術心得書』においては、「上段」を専らとし、「浮足」に構えての早業が特徴と記された直心影流が、『剣術名人法』では「其の事すたれて上段にさへ取る者も稀にして、一刀流の下段星眼となり」と評されているように、弘化・嘉永期には、竹刀剣術流派の技術的特徴の喪失がはじまり、竹刀打ち技術の画一化が始まっていることもみてとれます。これは、天保期の他流試合の解禁以降、廻国修行や藩邸御前試合などが盛んに行われるようになり、そのことが技術や用具の情報交換や共通化をもたらしたことに起因しています。
(つづく)
*この『剣道技術の成り立ち』は、2005年10月〜2006年3月まで6回に渡り月刊「剣窓」に連載したものを再掲載しています。