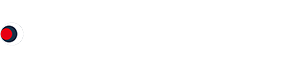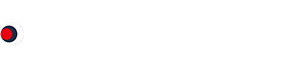図 書
剣道と「き」
第5回 「機・気」への着目
全剣連 広報・資料小委員会 委員
埼玉大学 名誉教授
大保木 輝雄
戦闘が収まった江戸時代の初期、武術家たちは戦場で会得した心と体の構えを、 極限状態における一対一の対峙空間にみたてた剣術の世界に凝縮させました。戦闘という「命懸け」の世界に身をおいた者だからこそ見出せた一筋の光明である「いのち」の根源への気付きを、殺生の術から「人を活かす術」として整理・再編し、身法、技法、心法の三位一体となった働きを体得させるための体系を作り上げたのです。
その代表的なものは柳生新陰流で、この流派の修行の目的は「機(気)をみる心」の養成にありました。自分の置かれた情況をしっかり見据え、退くことなくいかにその場を切り抜けていくか。その究極の手段を「身を捨てて勝つ」ことに見出し、実にシンプルな極意太刀(十文字勝ち)と、勝負の場における「気」の在り方を示しました。
以来、一触即発の場での心身統御法の中心課題として「気」を捉えた武士の精神性は、武芸として受け継がれ洗練されながら、剣道においては「気剣体一致」の精神として現代の私達に伝えられているのです。
1.機をみる心、機前のはたらき
柳生宗矩(1571〜1646)の『兵法家伝書』は、万物(人間)の本性と、その現象として現れる作用の関係論的認識に立脚し、実際に命のやりとりをした戦闘の時代を反映してか、仏教的な「機」(きざし、はたらき)を援用して「機をみる心」「機前のはたらき」をテーマとした心法論を展開しています。武術家にとって、相手に及ぼす力とそれを司る自分自身の在り方は重要な課題でしたから、元来は儒者や仏教者に見られる用語や視点が、己の体得した実存的地平を語るのに好都合であったことは、容易に推察できるでしょう。
『兵法家伝書』は、「心」には「本心」と「妄心」がある、としています。本心とは自己の本性であり、気が身体全体にのびひろがった「元気」な状態。妄心とは迷いの心であり、気が一カ所に固まった「病気」の状態をさします。「機をみる心」は本心であり、それを塞ぐ「心の病」である妄心は、「気」の集散をコントロールし妄心を排除すれば、おのずから本心が現れる。だからこそ「内心に気をはたらかし、うごかし、油断無くして、外は又ふためかず、静にする。是陽内にうごき、陰外に静なる、天理にかなふ也。又外きびしく懸なれば、内心を外にとられぬように、内を静にして外懸なれば、外みだれざる也。内外ともにうごけば、みだるゝ也。懸待、動静、内外をたがひにすべし」といった状態の心身でなければならないとしています。宗矩は「機・気」概念を導入援用することによって、新陰流兵法で会得した心身の在り方を『兵法家伝書』において解き明かそうとしたのです。
2.イメージから哲学概念へ
『兵法家伝書』に代表される江戸時代前期の伝書に共通するのは、それが流祖から弟子に受け継がれるべきものとして書かれ、勝負の場で獲得した個の「わざ」を集団技さらに政治論として発展させることに主眼が置かれていたことです。内容は「大機大用」「機前のはたらき」という言葉に示される行動理論であり、眼目は、行動の疎外要因を排除することにありました。それを表現する「気」の使われ方は、イメージを伝達するための概念の域を出ていません。
秘伝・口伝で伝えられた「武芸の本質」を解き明かし、分かりやすく人々に伝えたのが、江戸時代中期に登場した熊澤蕃山や佚齋樗山であり、彼らによって、武芸心法論は中国的気論を背景に理論付けされた新たな武芸気論として展開され、広まっていったことは、前号までに述べた通りです。剣術が低迷していたこの時期、樗山は「気」を形而上学的な哲学概念としてとらえ、剣術の目的を「練気養心」として生命の源である「気」の働きに着目し、剣術の稽古を媒介として「生死」の問題を解決せよ、と啓発しました。樗山の思想はその後、白幽仙人から授かったといわれる「内観の秘法」を公開した白隠(1685〜1768)の『夜船閑話』とともに、幕末の剣術家に多大な影響を与えることになるのです。
(つづく)
*この『剣道と「き」』は、2004年9月〜2005年9月まで12回に渡り月刊「剣窓」に連載したものを再掲載しています。