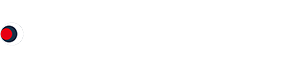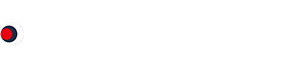図 書
剣道と「き」
第11回 現代「気」論の流れ
全剣連 広報・資料小委員会 委員
埼玉大学 名誉教授
大保木 輝雄
1991年、「気」を核とした学際的な研究団体として「人体科学会」が発足しました。きっかけは1984年にフランス国営文化放送と筑波大学の共催で行われた「科学技術と精神世界」というシンポジウムです。日本側が「気」をテーマとしたことで、欧米に「気」の概念が広く知られるところとなり、日中間の気功交流が始まるなど、80年代のニューサイエンスブームも手伝って、「気」という言葉が脚光を浴びることになりました。が、実はこのはるか以前から、日本には「気」をまじめにとらえ、考察を重ねていた研究者たちがいたのです。
1.「気」へのさまざまなアプローチ
美学者の中井正一は1945年、『気質』と題した論考を発表。日本語の「き」という言葉の持つ広い領域と種類における意味について「それが固定的のものでなくして、むしろ含蓄より発出に向うとの流動性をもっていること」とする共通項を見出し、「その傾動の位置、方向、運動に結びつくことによって、特殊の空間的性格をももってくる」と考察を進め、「心が何らか、中心、湖心、核心などのごとく、いわゆる求心的なるものをもつに対して、気は何ものか流動的発出的核心を意味するように思われる」と一応の結論を導きました。さらに中井は『気(け、き)の日本語としての変遷』の中で、記紀万葉から近松、芭蕉に至る日本文学に見られる「き」の用例を俯瞰し、とりわけ源平以後の軍記物語に、勝負の決定的瞬間に向かう凝集された時間ともいうべき「機」の感覚が芽生えていることを指摘しています。そこに「き」の大きな意味の転回を捉え、「一気通貫とでもいうべき『気』の言語意味は、かかる生活の極限状況の下に、自らの意味を構成し(中略)生活そのものもまた、自らの道(ロゴス)を発見し、自ら結晶してゆくのである」と、「き」の用例変遷をたどる中で日本人の中に芽生えた「近代意識」の出現の徴候までをも見出しています。
また、前号で取り上げた田中秀雄『武道の心理』にも序文を寄せている千葉胤成は、昭和28年に発表した「『気』について」という論考の中で、心理学の立場で、中国古典から西欧近代哲学、幸田露伴に至る「気」の問題を取り上げ、考察しています。
フランス哲学の澤瀉久敬は、東京オリンピック開幕前夜に行われた「からだの哲学」と題した記念講演で、人間の身体をめぐる発表を行いました。その中で澤瀉は、「生物はたんなる物質ではなく、それになにか一つの動的な原理がある(中略)私はそれをかりに『気』と呼んでおります」と述べ、「『気』によって身体は内に統一性をもち、外に対しては能動的となると考えるのであります。この『気』の内的統一性と外的能動性は正比例をなしており」、「身体に変化を与えるだけではなく、それ自身が進化発展する」と「気」の本質を捉えています。
2.「間」を往来する「気」
精神医学の木村 敏は、1972年『人と人との間』の中で、「気は一応は自分のものとして言われていながら、自分の自由にならぬもの、周囲の情勢次第でいろいろに変化するもの、その意味で『人と人との間にあるもの』」と位置付け、「気」は「元来は超個人的、宇宙的な概念が全く自然に個人的な『心ノ趣クトコロ』として使用されているということが、この言葉に不思議な、外人には理解しにくい性質を与えているのだろうと思われる」と書いています。木村の考察で重要なのは、「心」と「気」の成立基盤が全く違うという指摘です。前者は「もっぱら自己の主観的な状態、目の前にある対象とは無関係に一定期間自己の内部で持続する意識状態」であるのに対し、後者の「気」は、「つねに眼の前にある情勢や事物との関連が問題になる」ものだとしています。「気」をそのように捉えた上で、「主観と客観、意識と対象の『間』にあるもの」で、その動きの主体は自己の側ではなく「気それ自体の側にある」としています。これは、武芸における気の問題を考える上で、今日、究めて重要な示唆を与えてくれるものです。
お互いに向き合って打ち合うという剣道の非常にシンプルな関係性の中で、体験的には把握していても言葉にしにくい「立ち合い」の場に流れるものは何なのか。先にあげた優れた先覚者の言葉を借りると、それがあたかも霧の晴れるが如く眼前に出現するような気がします。
(つづく)
*この『剣道と「き」』は、2004年9月〜2005年9月まで12回に渡り月刊「剣窓」に連載したものを再掲載しています。