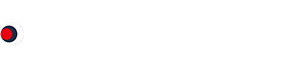図 書
剣道と「き」
最終回 剣道気論の行方
全剣連 広報・資料小委員会 委員
埼玉大学 名誉教授
大保木 輝雄
1.日本文化の要、「肚」
剣道を学ぶということは、どういうことなのか。それを考える時、外国人の視線は、私たちにある意味で「気付き」を与えてくれます。
『肚 人間の重心』(麗澤大学出版会)の著者、カールフリート・デュルクハイム(1896~1988)はドイツの哲学者で、1937年頃からほぼ10年間、ちょうど第二次世界大戦を挟む年月を日本で過ごしました。西洋の心身二元論的な人間の捉え方に限界を感じていた彼は、日本人の生活と心の持ち方に興味を持ち、日本語とともに弓道・書道・華道・茶道を学び、相撲にも通じたといいます。熱心に参禅をし、佚齋樗山の「猫の妙術」をも深く読み込んだという彼は、それら一連の日本の伝統文化に触れるうちに、そこに通底するものが「肚」であることを見出しました。
デュルクハイムは、「『肚』とは、人間がその根源的中心へと通じる力を見いだして、そこから自分が本物であることを確かめる心身状態」であるとし、「自我の成長と共に、自然の持つ根源力や秩序との結びつきは失われていくのが常である」から、身体の重心を「肚」に置くことによってのみ、人間は「『頭による知力』の支配から解放され、身心一如となった活動の場に住することができる」と説きます。そして、本質にかなった心身の状態を得ようとすれば「正しい姿勢、正しい呼吸、正しい緊張の修行」が拠り所となり、「全身全霊、その場に居合わせること、しかもその場にふさわしい役割を果たしつつ自己本来の存在を維持させるのが『肚』である」と喝破するのです。
このような指摘は適確で、剣道の立ち合いの場における心身状態を考える上でもたいへん示唆に富んだものです。
2.剣道を学ぶことの意味
同書は1950年代はじめに発行されて以来、大きな改訂を含め十数版を数え、ヨーロッパ各国語に訳され広く読まれています。原書に付いている付録の中には、白隠禅師の『夜船閑話』のドイツ語訳も含まれています。
デュルクハイムが『肚』を著した背景には、物質文明が栄え、知的レベルが高度になったにも関わらず、基盤となるべき精神はそれに付いて行けない、という当時のヨーロッパに蔓延していた危機感がありました。彼はそれを打破する鍵を日本文化に求め、同書を著したのです。しかし、皮肉なことに私たちが置かれている現在の日本の状況は、当時のヨーロッパの状況そのものになっているようです。明治維新以来、西洋から多くを学ぶことで近代化を成し遂げ、戦後はグローバリゼーションの波の中で奇跡的な経済発展を続けてきた日本。その過程で、私たちは『弓と禅』を著したオイゲン・ヘリゲルやデュルクハイムらが外からの視点で見出した「日本の文化に流れる本質」を忘れてきてはいないでしょうか。
剣道が広く国際化の道を歩みつつある現在、日本人であるというだけで「一本の思想」が分かるという錯覚は、もはや思い上がりに過ぎないのかもしれません。だからこそ、今、剣道を学ぶことの意味を、きちんと再考しておく必要があるのです。
3.一本と気
窪田清音が「心気理の研究は初学に益なし」と言ったように、剣道で「機」や「気」が問題にされるのは基本技術の習得が進んだ後のことです。それは、相手と対峙して自分の技を「いつ、どこで」使うかという課題を加えた地稽古や試合ができるレベルで初めて問題になるのです。打つべき機会を捉えた気剣体一致の「一本」の追求が心身の熟練度を深めていくことは周知のことですが、このような一本の追求は剣道実践者をいかなる場所に運んでくれるのでしょうか。
前回ふれた精神病理学者・木村 敏氏は、「間性」に言及する独自の気論を展開しています。「自分と相手との『あいだ』が、二人の真に『会い合う』場所となりうるためには、そしてこの『あいだ』の場所が、自分と相手との両者の『自己』を同時に成立させる自覚の場所となりうるためには、そこには『ま』と呼ばれるようなはたらきが十分はたらいて、二人がそれぞれ自己自身の歴史を生きながら、その『あいだ』においては、共通の唯一の時間の生成に関与しあっている、ということがなくてはならないのではないだろうか。『自己が自己ならざるものに出会った、まさにその時に、ぱっと火花が飛散るように、自己と自己ならざるものとがなにかから生じる』。この『なにか』が、さしあたり人と人との『あいだ』であるとするならば、『火花』は『ま』にあたるといっておいてよいだろう。―中略―『いま』と『いま』との『あいだ』に真の意味での現在があって、それが絶えず『すでにあったいま』と『きたるべきいま』とをわけている。そして、ここでも自己自身を絶えまなく二重の相に分極しながら既往と将来とを根源的生成の動きにおいて産出している『原時間』ともいうべきはたらきが『ま』とよばれるものなのである」(『「あいだ」と「ま」』)。つまり、木村氏は、「ま」の本質は、ものともの、あるいはこととこととの「あいだ」にはたらく「機」であり、「機」とはそれ自体「はたらき」であり、「はずみ」である、と言っているのです。
剣道では、お互いに向き合う距離を「間合い」といい、対峙時間を「間」というように使い分けています。特に「勝負」の場面では「間合い」を測りながら技を出すタイミング(機)、いわゆる「間」が重要な課題となってきます。そこで、木村論に沿って剣道を考えてみると、機会を捉えることは、「ま」の本質を探ることに繋がり、「あいだ」性の自覚を促すことになります。
そう考えると、剣道の修行とは、自分とは何か、敵(相手)とは何か、彼我を生かしている「いま、ここ」という場とは何かなど、それぞれが織りなす関係性への「気付き」を促す行為そのものだといえるのではないでしょうか。
4.これからの剣道
そのような「気付き」のレベルは「一本」の完成度によって量ることができます。逆にその「一本」が新たな「気付き」へと無限の追求を可能にし、常に完成度が洗練され続けるのです。理想的には、自分の心と体を一体として働かせ、迫り来る相手からの圧力感に影響されることなく、打つべき機会に間髪を入れず自在に一本が繰り出されるようになれば申し分ありません。そのための心身のあり方を、古人は「上虚下実」と言い表しました。それを柳生流では「下作り」といい、腰の周辺の充実を強調しています。「志は気の帥なり」という文言の「志」は、身体性に即した解釈から「下作り」のことだとされます。その後、白隠の「練丹」法が撃剣に導入されていきますが、そのような流れは近代剣道に関しても継承されています。
菅原 融は『学校剣道原論』の中で、「剣道は、精神内容をふやす点には無力だが、精神鍛練においては他の学科に及ぶものがない」と述べ、「剣道の四病を除く姿勢(腰椎を折らず下腹に力が入る)を取り全身の力の中心に力が入る。この姿勢がくずれなければ四病をさくることが出来る。これが精神鍛練の基礎のものであることを先ず生徒にのみこませることが肝要である」と説きました。
このように、日本の土壌で育まれた「練気養心」の思想は、各時代の表現の差こそあれ、身体の問題として「腰・腹」中心文化を築き、デュルクハイムをして、「肚」の人間学的意味を「『肚』は、だれにも備わっている、より大きな生命の力と人間とを根源的に結合するという本性をそなえている」と言わしめたのです。デュルクハイムがあらためて見出したこの「本性」こそ、「気」の正体です。
ソニーの名誉会長だった故・井深大氏は、1984年に行われたシンポジウム「科学技術と精神世界」に出席し、「考えるよりもまず感じることが大切だ」という感想を持ちました。そのシンポジウムがきっかけとなり、「人体科学会」が発足したのは、前号で紹介した通りです。井深氏は「人体科学会への期待」として、「『気』を具体的な言葉や数字で表現しようとする考え方は、ある意味ではたいへん間違いですね。言葉とか文字とかに表せないのが『気』の本質だと思います」という言葉を残されています。
気の正体解明の唯一の手がかりは、まずは、心と体の座標軸を腰腹に治めることです。既に与えられているこの身体のカラクリ(存在の根拠)を剣道によって解いた先人の血と汗の結晶を我々が如何に認識し継承するかが問題となるのではないでしょうか。
(おわり)
*この『剣道と「き」』は、2004年9月〜2005年9月まで12回に渡り月刊「剣窓」に連載したものを再掲載しています。