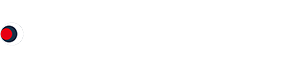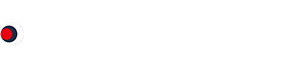図 書
剣道みちしるべ
第11回 「真剣勝負の精神」について
総務・広報編集小委員会(当時)真砂 威
第6回剣道文化講演会(2007年12月1日)の抄録が『剣窓』2008年2月号に掲載されていますが、「第二部『心の修行と現代剣道』」の中で森島健男範士は、「『剣道指導の心構え』について」で次のように述べておられます。
〈剣の理法が「日本刀の刀法」だとすれば、「竹刀は刀」という観念は当然のことです。これが日本の剣道の伝統なのです。ですから、真剣勝負から始まった剣道は、たとえ競技方式でやっても「真剣勝負の精神」はずっと残さなければいけません。これが無くなると、剣道の意味も無くなってしまうと、私はそう思います。〉
先月号で、「真剣味再現」と申しましたが、まさにこの「真剣勝負の精神」のことなのです。どこを斬突してもかまわない往古の日本刀での対峙であれば、防御の体勢はどんな格好であっても、そのまま真剣勝負なのです。先月号の挿絵のような、いわゆる「三所避け」様の構えも当然あるわけで、それぞれが「懸待一致」に根ざした身がまえにほかなりません。ところが、打突部位を限定した現代剣道において「三所避け」を駆使した、「懸」「待」分離の試合では、「真剣勝負の精神」が置き去りとなってしまいます。これでは「不動心」「忍耐力」「克己心」「情動抑制力」などを鍛え上げるという剣道の特性が失われてしまいます。
ところでこの「三所避け」戦法ですが、かなり昔からこの防御を得意とする選手がいました。学生剣道の歴史の中には、この防御法を使いこなすことによって勝利を収め、一時期注目された選手もいました。「うまいこと避けるなあ」と、評判にはなりましたが、うらやましいとは思われなかったのでしょう、流行るまでには至りませんでした。時代背景が違うのかもしれませんが、たぶんこの姿勢をとること自体が″卑怯″とか″かっこわるい″という共通認識があったからだと思われます。また、打たれまいとして、この姿勢をとって戦うことは精神的な弱さのあらわれと思われていたのでしょう、ほとんど問題視されることはありませんでした。
時は移っていま、この防御姿勢が流行りだしたのは、先々月号「時代とともに」での佐藤康光永世棋聖の言をかりると、「社会情勢と似て世知辛くなった」ということかもしれません。それはともかく、″避け″に終始したあげくの果て、相手の油断を待って技を出す戦いは、試合の長時間化現象をもたらしました。
卑近な例をあげれば、″グー無しジャンケン″のようなものです。パーを出したら負けるので、双方ともチョキを出して守り続けるしかない。エンドレスです。チョキ、チョキ、チョキ…。疲れ果て、つい片っ方の手が″パー″と開いた、とたん「勝負あり」という譬喩が当てはまります。
戦前の天覧試合などでは、「防御一辺倒の姿勢」や「粘りつく鍔競り合い」は皆無であったと前に申しましたが、勝負に要する時間も非常に短いものでした。その当時において、思いのほか長時間に及んだ試合では、「15分にも及ぶ長い熱戦が…」などと異例に扱われています。そして選手は「疲労困憊の窮み…。天皇陛下の御前でなければ私はその場でぶっ倒れていたでしょう」と、勝った時の感想を生々しく述べています。15分で疲労困憊ですから、どんなに真剣度が高かったかがうかがい知れます。最近では、30分以上も平気で戦っている試合も珍しくありません。″元凶″は見えました。この防御の姿勢をやめ、鍔競り合いが瞬時に解消されるようになれば、もっと短時間で勝敗が決し、「真剣勝負の精神」が生かされた試合展開になると思われます。
これに対して一方では、「三所避け」戦法には、「左胴技を奨励すればよい」ということがよく言われます。また実際に左胴技を駆使した試合もよく目に触れるようになり、有効打突の要件・要素にかなえば一本と認められています。しかし、これを当然の道理としてよいものでしょうか。
(つづく)
懸待一致:攻撃はそのまま防御になり、防御はまた、ただちに攻撃に転ずるための構えとなる。攻撃と防御とは一体であるということ。(加藤 寛・西村 諒編、『日常語の中の武道ことば語源辞典』東京堂出版 1995年7月20日発行初版より)
*この『剣道みちしるべ』は、2007年8月〜2010年1月まで30回に渡り月刊「剣窓」に連載したものを再掲載しています。