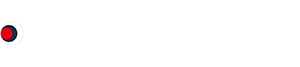図書
『令和版剣道百家箴』
「私の剣道人生」

剣道範士 幸野 實(神奈川県)
私が今日あるのは剣道のおかげです。今日までよく続けてきたと思います。時々の苦労や体験は、先師、先達の導きの賜物です。ひたすら剣道を続けてきただけに過ぎない私が、将来ある次世代の指導者、剣道修行者の参考になるのでしょうか。体験の一端がなにか少しでもお役に立てばと筆をとりました。
剣道を習い始めたのは、秋田商業高校1年生の時からでした。今から65年以上も前のことですから、記憶も薄れています。当時の剣道部は戦前からの歴史と伝統が続いていて、先輩からの勧めで入部はしたものの、切り返し、打ち込み、かかり稽古の連続でした。体力のない私にとって、とても厳しく、毎日の稽古についていくのがやっとでした。
指導をしてくれた先生は、修道学院で修行をされた加藤正治範士。30代半ばの鍛えぬいた体格で、毎日稽古をつけてくれました。息も絶え絶えに必死にかかった思い出があります。当時剣道を続けるか悩んだ時期もありました。インターハイで優勝したことがきっかけで、昭和34年高校を卒業と同時に神奈川県警察に特別採用され、剣道特別訓練員として、本格的な剣道の修行がはじまりました。当時、神奈川県警察には、井上研吾先生を筆頭に菊池傳、高野武、中村太郎他大勢の師範がおられ、ただただ強くなりたい。その一心で稽古に励みました。
勝負の結果で左右される世界に長くいたためか、若いころは気が付かなかったのですが、自分の剣道修行に偏りが生じてしまったのかもしれません。試合に勝つためにいかに早く竹刀を振るか。目先の勝ち負けにこだわり過ぎたと感じています。恥ずかしいのですが、80歳を超えて、身体も効かず体力も落ちて、ようやく気付いたことがあります。それが剣道の特性だと思います。剣道は、試合、勝ち負け、結果だけではないということです。相手を思い、共同し、修行は技術の向上だけでないということ。その過程で自分を高めることになります。
私はそんな大事な当たり前のことを理解するのが十分ではありませんでした。勝負ばかりにこだわり、本来の剣道の修行に必要なものを見落としていたのではないか。人間としての道を求める修行が足りなかった。その結果、剣道人口が減り、子供が上達するか否かなども、すべては自分の鏡であったと思うのです。「日暮れてなお道遠し」の心境です。
剣道は他のスポーツと同じようなルールや試合の結果を重視するようなことではいけません。子供たちに礼節を説いても、あるいは信義を重んじるように伝えても、反応は乏しい。興味を持つのは目先のゲーム感覚でしかなく、結果長続きしない。やめてしまう子も多い。現在の剣道における課題と、危惧するのは、私だけではないようです。
我々の時代の先生方は、技術や精神面の修行など細部まで弟子に指導はしてくれませんでした。そんな中である先生が「いいか。剣道をやってきたからと言って、必ずしも立派な人間になれるものではない。」ということを教わりました。一貫して剣道に携わってきた自分が言うのもおかしいのですが、最近そのことを思い出します。
剣道の修行を通じて得たことはなにか。今後の指導に役立ててもらいたいことは、剣道をしていれば、「苦しいことに耐える」「つらくても逃げない」ということに結びつきます。気が付くと私自身の人生の土台になっています。
範士八段をいただいたとしても自身の剣道は修行半ばです。剣道をする人口が少なくなる。指導者がいないので、剣道部を廃部にする。そんな報告を受けています。剣道連盟の会長として何ができるか、多くの方の力を借りて課題に取り組んでいます。並行して指導者がスピードや打ちの強弱、剣道形や刀法などを本当に理解してくれているか。剣道は勝負や審査のためだけではないということを伝えてくれているのか。少し疑問です。
私自身が剣道に従事するすべての方の共通する課題に、もっと早くに気が付くべきでした。人生そのものに必要な「当たり前のこと」を教えるのが指導者です。すべては自分の鏡であるということ。剣道の将来を支える皆さん一人ひとりが気づいてほしい。人間形成という言葉の中にある、本当の剣の道とはどのようなことか。自分にとって今なにが必要で、どのような意識で剣道の修行を続けていくべきなのか。そのことを曇りのない心の目で見つめてほしい。そんなことを申し上げたい。(受付日:令和6年7月24日)
*『現代剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。