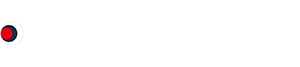図書
『令和版剣道百家箴』
「剣道修業において大切なこと」

剣道範士 岡田 一義(三重県)
私は戦前の昭和17年3月生まれです。戦後、剣道は敗戦のため中止を余儀なくされ、昭和25年スポーツ的要素の強い撓競技として開始され、昭和27年全日本剣道連盟が発足、剣道が復活しました。撓競技の撓は手元以外は十六割で布袋がかぶせてあるもので、面は網目になったもの、胴と垂は一体となった防具で、剣道着は刺子で下はトレーニングパンツ、試合は時間内に何本でも取得でき、所得本数の多さで勝負を決めるものでした。本来の剣道が復活後は年を経るごとに盛んになり、昭和の後半から平成時代には、特に小中高大学に加え、高齢者、女子の剣道人口も増加し、隆盛を極めるものとなりました。その当時の剣道(特に少年)を始める要因として、本人からすると、かっこよい、おもしろそう、友達が入るから、家族がしていて、勧められた。家族からしてみると、礼儀正しくなる、姿勢正しくなる、挨拶ができる、体力がつく、集団生活になじむ、家族がしている等。人によって異なりますが、続けるうちに剣道本来の良さを覚え、続けるようになります。平成の後半から令和の時代になりますと、全人口の減少に加え、スポーツの多様化、また小学生時代は、スポーツ少年団や地域の道場でしていたものが、中学・高校になると指導員不足の為に止めてしまう等、少年剣道人口の減少が深刻化し、減少をくい止めるべく対応が迫られ、今後の大きな課題となっております。
令和2年から約3年間は、新型コロナウイルスの感染症の大流行から、全剣連以下、全国的に稽古や各種行事等を中止せざるを得なくなりました。3年間で感染者約3,100万人、死者約62,000人で、全剣連の防止策として、シールド、マスクの着用、新型コロナウイルス感染症が収束するまでの暫定的な試合審判法が適用され、対策が図られました。特につば競り合いからお互いに別れることにより、不当なつば競りの違反がなくなり、好評となりました。現在、収束しつつあるものの完全な収束ではなく感染防止対策を取りながら、各種運営を図っている現状であります。また、時代の変遷とともに人権や組織管理等、各種問題に的確に対応する必要性から、各種ハラスメントやガバナンス・コンプライアンス等の問題に対応する組織運営が図られております。
剣道修業の大切なことを申し上げますと、基本の大切さです。立派な大木も幹や枝葉を見て評価しがちでありますが、木を支えているのは根の部分で、立派な根の張りが丈夫で素晴らしい木となって見えるものです。剣道におきましても、基本と言いますと、有効打突の要件、要素をとらえ基本と思いがちですが、剣道の理念・修業の心構え・着装・礼法・所作・足さばき等がしっかり身について立派な剣道となるもので、高段位になればなる程、基本(基礎)の上に有効打突の要件・要素が必要であると思います。
私が大切にしております訓えは、「三位の格」で
○露の位
「木の葉に落ちた水滴が静かに凝集して機満つればポタリと落ちるよう決して無理な打ちを出さず静かに機が至るのを待ち、相手の動きにしたがって隙を見つけ瞬時に技を発動して勝ちを占める」の教えにあるとおり、いかに相手の虚すなわち打つべき機会を作りあげるかが重大で、そのためには中心を外さず、先先の先の気持が大切で、機会については知る(気ざしを察知)乗る(打ち勝つ)作る(気・剣・体の攻め)。
○石火の位
「火打石を打てば火が出るように機至れば間髪を入れず鋭い打ちを出す」すなわち鋭い打突とは、気・剣・体一致した冴えのある打突である。冴えは打突の瞬時の速さと強さである。
○梵鐘の位
「打てば即ち梵鐘のように余韻嫋々たる気の残心を漂わすこと」有効打突の要件に残心あるものとされているとおり、打突後油断することなく相手に自由自在に対応できる気剣体の構えが大切で特に残心は品位・風格の大切な要素である。
剣道をする上で、誰しも強くなりたい・試合に勝ちたい・昇段したいとの目標は、自分を向上させるために大切なことで、目標を達成するためには、日々の努力が大切で、よく努力は報われる、結果がでる、やった甲斐がある、嘘をつかない等と言われ、目標を達成するための大切な言葉であります。
歴史とともに進んだ伝統文化である剣道が的確に伝承され、今後益々発展することを念願するものであります。(受付日:令和6年6月8日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。