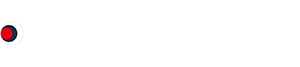図書
『令和版剣道百家箴』
「三つの要」

剣道範士 宮川 英俊(福岡県)
これまで剣の道を歩いてきて、何が必要で何を一番大事にすべきかを考えてみました。第一は、「基本を大切にすること」です。皆さんは「基本」というと、まず思い浮かべるのは、技としての基本ではないですか?私が言いたいのは“人としての基本”、つまり礼儀を重じるということです。そして礼儀の原点が「あいさつ」であると思います。
ところが近頃、この挨拶がきちんと出来ない方が多くなった様に感じられます。剣道では、“礼に始まり、礼に終わる”と言われますが、正しい礼の原点がこの「あいさつ」です。何も道場内での挨拶が全てではなく、朝起きて「おはよう」から夜寝る時の「おやすみなさい」迄の全てが挨拶だと思います。
学校で先生友達、職場で上司、同僚への挨拶もあるだろうし、道場に来れば出入口での礼に始まり、指導してくれる師、先輩、仲間への挨拶、更に稽古の時は「お願いします」と言ってますよね。この礼は「今から私の修業と上達に御指導御協力下さい」のお願いであり、終りの「有難うございました」は、「皆様のお蔭げで素晴しい修業が出来ました」という感謝の礼だと思います。剣道は、決して一人では上達出来ないのです。色んな方々の支えがあってこそ、一人前になれるという気持ちを忘れない為の礼法が必要ではないでしょうか。是非、気持ちの良い「あいさつ」を心掛けて頂きたいものです。
次に大切なことは、「聴く耳を持つこと」です。誰でも剣道を始めた時は、一日でも早く上達したいという気持ちから、教てくれる先生方の言われる言葉を一語一句聴き漏らさず、竹刀の握り、構え、足運び、面の打ち方等、素直に行っていたと思います。そして初段になり、有殺者として上を目指して、努力精進してこられたのではないですか?その姿勢がある程度の高段者になると“俺が、俺が、俺が努力してここ迄来たんだ”という変な自我が芽生え、最初の頃の素直な気持ちから逸れていき、方向性を見失ない、最終目標に到着出来なくなっている方が見受けられます。
指導したり色々助言してくれる先生(先輩)方は、その人が見込みがあるので、ここを少し変えればもっと良くなるとの思いから、厳しい言葉も掛けてくれるのです。それを自分は今迄これでやってきたからここ迄なれたという気持ちが邪魔をして、素直に言われることを取り入れようとする気持ちが無い為に、せっかく目の前に来たチャンスを掴み損ねることになるのです。どうか剣道を始めた時の“初心”に立ち返り、是非、素直に聴く耳を持って貰いたいものです。
かくいう私も八段に挑戦する2年前に、ある道場に稽古に行った時、そこに来られていた一人の先生から、「竹刀を持って構えてごらん」と言われ、その通りにやってみると、「何段ですか」と問われ「七段です」と答えると「よくそれで合格出来ましたね」と言われた時のショックは、言語に表わせませんでした。七段迄、全て1回の受審で突破してきたという自負心が無残に打ち砕かれました。その後、何度稽古しても、全て“先の面”に跳ばれ「私を打ちたいなら墓石を打ってね」とまで言われました。その先生の信条は、”面が打てれば、後は何でも打てる”でした。
それからは、その先生の言われるまま2年間、只ひたすら面打ちだけの稽古を続け、そのお蔭げだと思いますが、2回目の受審で、最大の難関と言われております八段に合格することが出来ました。
最後に言いたいことは、せっかく始めた剣の道。“一意専心”の気持ちで、生涯続けて欲しいものです。私も剣道を始めて、70年余になります。子供の頃は運動オンチと言われ、何をしても他の方の足手纏いになってました。剣道を初めてもなかなか思うような結果が出せず、何度も挫折しそうになりましたが、その気持ちを支えてくれたのが家族の声援でした。
大学卒業する迄、あらゆる大会に応援に来ては、勝ち負けに関係なく「素晴らしかった、良かったよ、惜しかったね」との声援で、この家族の喜ぶ姿を見たい為に頑張ってこれたと言っても過言でなく、これ迄続けていられた一因だと考えます。
又、こうして続けてきたからこそ、今人前に立てることが出来る迄になれたと思います。残りの人生、竹刀が握れなくなる迄剣の道を歩み続け、斯道の普及発展に微力ながら、精進の日々を送りたいと思っております。
「継続は力なり」「生涯剣道」この精神こそが剣道の原点だと考えます。(受付日:令和6年7月22日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。