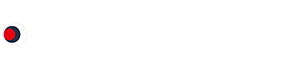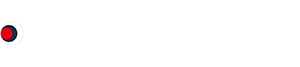図書
『令和版剣道百家箴』
「生涯剣道と私」

剣道範士 小笠原 宗作(東京都)
昭和27年、戦後の混沌とした社会。生徒会の総会でクラブ活動として、剣道部が創設された。私は家族と相談の上、剣道部に入部。①人の道に反しない道徳心②姿勢が良くなる等。身に付ける剣道具は各自持参し、場所は青空天井、校庭の片隅、先生、先輩方の指導のもと、土まみれなり、基本中心に素振り、足さばき等。
卒業時、就職難で先生から、剣道を続けたいと希望があるなら本格的に警視庁に、との助言が有り、警視庁を受験。1年間、警察官に必要な教養を受けた。剣道は正科でした。
「のびる若竹 親竹こえる 親をこゆるも親の恩」。卒業後、各警察署に配置され、仕事をすると共に、各大会に参加。体育専科(武道と云う言葉不可)受験。1年間、体育専科生として修業(外部講師により体育心理学、剣道理論等)、1週間、鎌倉建長寺にて座禅「座して半畳寝て一畳」数息観(呼吸法)、精神教育を受ける「警視庁に助教、教師、師範と云う制度有り」。
専科を卒業すると、助教候補として各機動隊に配置され、隊員の指導と自らの研鑽。
「聞くは一時の恥 聞かざるは一生の恥」。
「構え」 ①立つ姿はのびる杉ノ木の如く、②目は遠山を見る如く、③腕は赤子を抱く如く、④握りは鶏卵を握るが如く、⑤持つ手は、小指半分竹刀の柄頭を持つ。こぶしににわを作らない、⑥足は水鳥の如く、⑦攻めは表裏から乗って崩す(剣を殺し気を殺し技を殺して打突する)
「切り結ぶ 大刀の下こそ 地獄なり 一足ふみ込め あとは極楽」。
技を出す時は、無心になって全身の力と気迫で打ち込む様に心がけて初太刀を大切にして稽古しているが、未だ至らず。今後も努力していきたい。(受付日:令和6年6月20日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。