
図書
『令和版剣道百家箴』
「私の剣道の原点と現在」
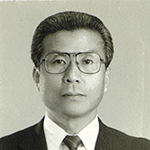
剣道範士 脇本 三千雄(宮崎県)
Ⅰ.長い戦争の時代
昭和8年(1933)5月、満州事変は一応終結し停戦協定が締結されたものの国際的孤立が始まり、昭和12年(1937)7月に日中戦争が始まった。日中戦争は、中国の門戸開放政策をとるアメリカを著しく刺激した。私はこの年の11月に宮崎県南那珂郡北郷町で生まれた。戦争は昭和20年(1945)に入ると敗色が濃厚となり、米軍の都市への空襲、広島・長崎が原爆により破壊された。当時の人々が生き延びるのに懸命の日々であったことを強く記憶している。同年8月、ポツダム宣言を受諾し、終戦(敗戦)を迎える。アメリカ軍の占領政策の第一は、日本の軍事力とその基盤の破壊・無力化であった。その為の施策は政治・経済の広範囲にわたっていたが、教育面はその中の最重点の一つになり、文部省は同年11月と12月の二度にわたり全国の教育機関に「体練科武道(剣道・柔道・なぎなた・弓道)の授業は中止すること(11月6日)」の通達を出した。昭和21年(1946)1月には武道教員の教員免許の無効化、通達に基づいて日本各地の学校では剣道具を焼却したり、土中に埋めたりしたところが少なくなかった。8月、経済復興の兆しが見えてくると各地において剣道のグループが出来てきた。剣道は確実に生き続け、稽古が行われていた。
Ⅱ.剣道の復活と学校教育への位置づけ
昭和25年(1950)3月、全日本撓競技連盟が設立。学校教材として採用してよいこととなった。対処療法として考案された撓競技は、今にしてみれば関係者の焦りでもあった。剣道の回復に思いを致すべきであったように考える。昭和27年(1952)10月14日、全日本剣道連盟の結成が決議された。この時、私は中学3年であった。
昭和28年(1953)5月に文部省社会局長から「剣道の禁止」の解除が通達された。武道としてではなく、体育スポーツとしての扱いで、「高校以上の学校において実施しても良い」の通達が同年7月7日付けで出され、敗戦後の禁止からやっと解除された。私は、宮崎県立高鍋高校剣道部が設立されたこの7月に剣道を始めた。当時の高鍋高校には道場がなく稽古はグラウンドの土の上で始まった。
昭和32年(1957)3月30日、保健体育審議会は文部大臣に「剣道を中学校の体育教材として実施」を答申。5月20日に従来の「しない競技」と「剣道」を整理統合し「学校剣道」として中学校・高等学校の正課体育として行うことができるようになった。
昭和33年(1953)の教育課程の改定で剣道を「格技」の名称で導入されたが、これはそもそも戦後の武道教育取り扱いの時代の経緯を踏まえたものである。
平成元年(1989)3月、教育課程が全面改定され、格技から「武道」へと名称が改められた。現在、中学校保健体育で武道の必修化が進んでいる。
平成18年(2006)12月、教育基本法の改定により、教育の目標に「伝統文化の尊重」が掲げられた。このことから「武道は日本の運動文化や伝統を知るのに役立つ」と判断され、平成19年(2007)9月4日中学校保健体育の教科で「武道」を1・2年の必修として実施が決まった。
Ⅲ.中学校教師としての38年間
私は昭和35年(1960)3月に国士舘大学を卒業し、中学校教師として東京都内の5地区(品川区・中野区・保谷市・武蔵村山市・中野区)7校で勤務した。就職1年目から「格技」として剣道を取り入れ、中学校の運動会では剣道の公開演武を行った。昭和39年には、16ミリ映像で体育教材の「学校剣道の基本」を制作した(学研)。はじめは撓競技でスタートした剣道であったために、剣道具は面・胴・小手・垂を使用しつつも竹刀は袋竹刀を使用した。私が部活動を指導し始めたときには、四つ割の竹刀を使った。授業用の剣道具が生徒の数だけ揃うと竹刀と剣道具の管理に苦労した。授業期間は冬季のみ3週間のカリキュラムで行ったので、使用しない期間が長く、いざ授業を開始する時になると面のカビがひどく、使用する前に45個の面を天日干しし、カビを取りアルコール消毒した。竹刀はひび割れや、ささくれ等の修理に多くの時間を割いた。時間が経過して竹刀は個人持ちにすることができた。授業は集中して行うために、面と小手の管理には特に気を使って消毒を行った。
Ⅳ.国士舘戦後の再出発(私の剣道の原点)
国士舘専門学校は、戦後、国士舘大学に名称変更され、国士舘は再出発した。体育学部は、体育科3年制の短期大学のスタートであった。私は国士舘大学体育学部の1期生として入学した。体育学部は約150名の入学生のうち剣道部は16名。全員入寮制で火気厳禁、暖房設備なし。150名のうち、2週間の夏休み明けには多くの者が退寮していった。
剣道部は通学生を除いて寮生で、朝稽古は日曜日を除き毎日5時起床、5時30分から1時間行われた。朝稽古後はキャンパス清掃をして、その後に朝食。授業は講堂・柔道場・剣道場の床に座っての座学が多かった。
剣道の朝稽古は、道場の床拭きから始まる。冬は、拭いた後から床が白く凍る日もあり大変だった。また剣道場は戦時中、世田谷区役所に貸し出されていたため、床は荒れ、通常の剣道場の床にするのに、長い時間を費やした。
指導者は部長が大野 操一郎先生(八段)、師範に斎村 五郎(十段)、小川 忠太郎(八段)、堀口 清(八段)、小野 十生(八段)、阿部 三郎(八段)の先生方と高校教師の伊保 清次先生(八段)が加わった。朝稽古に柴田 徳次郎館長が時々、切り返しを受けにこられた。7名の指導者が揃った稽古は、切り返し、打ち込み、掛かり稽古、指導稽古と続けられ、一人の指導で息が上がる程の徹底した厳しいものであった。
剣道場は木造平屋建てで幅7間、縦30間、柔道部やレスリング部も使用した。剣道場の床はスプリングの良く効いた床で、正座していると跳ね上がった。床下にはカメが埋められ響きも良かった。
このような立派な道場で4年間修業、入学時には初段であった私も、卒業時には五段をもって、卒業した。大学の4年間は剣道の技術のみでなく、人間として人格の高揚になった。
エピソードをいくつか挙げれば、身長186センチの伊保 清次師範(上段)と身長156センチの沼田 忠男(長野県出身)の稽古のこと、国士舘で初めての八段審査一次合格した柳井 秀一の審査のこと、第5回全国優勝大会2位を柴田 徳次郎館長に報告にゆくと「国士舘に2位はない」と賞状を破かれ中山主将はしぶしぶ賞状を拾ったこと、世田谷六大学剣道大会の優勝を報告すると、柴田館長は大変喜んで牛肉の差し入れがあったこと。この時、柴田館長の心意気を感じ、以後心して報告したことなどがある。
Ⅴ.剣道八段への挑戦(審査制度の変更)
私が剣道七段を取得したのが昭和46年(1971)、34歳だった。それから12年後に初めての審査に挑んだのは、これまで修業してきた剣道を審査員に評価し認めてもらう最後の機会と考えたからだ。実技1次審査員7名、2次審査員15名の審査員の前で力を示したかった。国士舘の1期生として、また全国中体連部長としての責任も感じていた。このとき合格するまで挑戦し続ける覚悟をした。しかし現職にあって稽古に十分な時間をかけることができず、稽古に工夫を凝らし、素振り、ストレッチ、一人稽古(剣道形)、週1回の稽古は貴重なもので集中した。国士舘専門学校卒の釘田 一男先輩に、切り返し、打ち込み、地稽古、掛かり稽古と一気で順に続ける稽古、この集中した稽古は大きな力となった。
平成9年(1997)5月7日、ホテルを8時30分に出て、9時受付、9時15分実技一次審査開始、剣道形審査(刃引きの刀使用)は午後3時を過ぎていた。二次審査が開始されたのは午後5時を優に過ぎていた。二次審査が終わって発表、合格者は6名、この中に私の受験番号があった。最後の審査学科審査は武道センターの地下道場。問題用紙を手にして3問に挑戦、身体全体に疲労感が伝わり汗で用紙は濡れ、シヤープペンの芯はポキポキ。会場を出たのは夜9時を回っていた。その日に東京に帰る気力がなく、教頭に電話して明日朝一番に学校に出勤することを約束。ホテルの地下の寿司屋で一人祝杯を挙げた。のどを通る酒は心地良く、一日の審査を振り返った。日本酒は最高にうまかった。精魂尽き果てた一日の眠りは深かった。
テレビは、大変な力を持っていると思った。NHK金曜ドキュメント「心で闘う120秒」で、剣道八段審査の模様が全国に放送されると、全国から久しく連絡が途絶えていた友人や、知人から祝いの電話が沢山入ってきた。剣道八段審査が大変な審査であることが、この放映で広く全国に知れ渡った。
Ⅷ.剣道指導の場(地域武道と学校剣道)
これまで多くの時間、学校剣道を中心に剣道指導に当たってきたが、現在地域の青少年と一般社会人に剣道指導を行っている。
少年指導の力点は、基本の徹底である。初めて竹刀を持つ子供たちに、一番大切な礼法、姿勢、発声、竹刀の扱い、手の内、体の運用(足さばき)の徹底を欠かさず、指導を続けている。
地域での剣道指導は、学校剣道(同じ指導者と指導体制)の指導と違い多様である。既に剣道を経験し、多くて週1回、長い休み明けに始める人、子供の付き添いで道場にきて初めて竹刀を持つ人、お母さんになって始める人、若い時に激しい稽古を経験してきた人、指導者に恵まれた人、仲間でレクレーション的に行ってきた人などが混在し、基礎・基本が徹底していない人も多い。
指導者は、年齢や経験度に大きな差のある人の集まりを指導するときは、一人一人の違いをどのように正しく認識し、声がけをするかが大切である。少年には1回の稽古で1回は褒めることをして欲しい。生徒にとって1日1回も声がかからずに終わっては、剣道の面白さが伝わらない。必ず何か一つでも良いところを見つけ褒める努力をして欲しい。また前回指導(声をかけたこと)したことを忘れてはいけない。次の日に褒めて欲しい。
また指導者の立ち位置は同じ場所にとどまらず、左や右に動いて見てあげる。特に子供や初心者の指導はそれが大切だと思う。
(参加者が)次の稽古に期待を持って明るい顔で参加できることは大切である。指導者としても励みになる
Ⅸ.剣道範士号の受称
平成19年(2007)5月6日京都において範士号の審査が行われ、5人の範士が誕生した。50代1名、60代3名、80代1名であった。範士の付与基準は「剣理に通暁し、成熟し、識見卓越、且つ人格徳操高潔なる者」と定められている。私は範士号拝受より19年を過ぎ、87才の齢を数える。原点に返って剣道を見つめ心の修業を中心に考えたとき、多くの課題がある。健康は大切である。(受付日:令和6年7月5日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。





