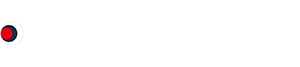図書
『令和版剣道百家箴』
「剣道を始めた動機、ー導いて頂いた先生ー」
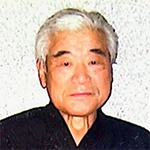
剣道範士 井上 茂明(奈良県)
1975年、愚生35歳の時、剣道理念が出来ました。理念作成の委員会は松本 敏夫先輩でしたので、内容について前もって知っていました。「剣の理法の修錬・・」の文章のところで、最初は剣の理法の剣がなかったのを覚えています。その年の6月、奈良柳生で中堅剣士講習会があり、私は奈良県代表で加えて頂きました。この講習会は35歳から50歳までが参加でき、約50人の規定がありました。
小川 忠太郎先生が早朝の座禅の時、「剣道は命がけで稽古するものです。理法の修錬ではありません。命がけで稽古します。」と剣の理法についてお話がありました。
「剣の理法の剣とは命懸けと云う意味です」とお話がありました。「刀で切られると後戻り出来ないと云う意味です」とお話をいただきました。私は33歳で七段を頂いていましたので、一番前でお聞きしていました。凄い迫力で目が合ったのを覚えています。以来、いつも稽古の時は大きな声を腹から出し力いっぱいで、打込んでいます。
野間道場に行く機会があり、懸命に稽古に励んだのを憶えています。その時、松本先生は自分の稽古を中断し、私の稽古をみて頂くように持田先生にお願いしてくれました。稽古が終わり扇形に正座して持田先生の今日の反省のお話を聞いた時、先生が一番後の私の方に近づき、「井上さん今日の稽古は良かったですよ。」とお誉め頂いたのは、私の宝となっています。後で松本先生から「一本一本力いっぱいに打込み、3分位で息が揚がる、良い稽古だった」とお話しいただき、今日も大事にしています。
力いっぱい打込むとき、何時打込むか?打込んだから相手に勝つのか?勝ってから打込むのか?最近は同じ事と思ってます。最近の稽古は駆け引きが主であり、1人当たりの稽古時間が長いと思われます。
奈良の西川 源内先生は会社の方までお電話を頂き、「今日何時まででも待ってるから奈良道場へ来い」とお声をかけて頂きました。それで稽古をお願いしますと、「今日はそれでいい、でも次のステップがある」とお話を頂きました。「剣道は『先』が大事だ」と、お教え頂きました。
「48歳になれば、八段受験できる、今年申し込め」とお話を頂き、48歳になったばかりの5月、京都の受験。大きな声で甲手、体当たり、甲手面、と打ってでたのを憶えています。試験が終わると、息があがり、ふらふらになったのを今も憶えています。
警視庁西山さんが、私の受験の相手の一人、甲手、面、体当たりをしたのを憶えています。
剣道とはなんだろう?2015年の剣道世界大会で、「稽古でどうして強くなろう、どのような稽古方法がよいか」を話し、切り返しの模範を自分で行い、説明中に、あるお方から突然に質問があり、「剣道の理念に『人間形成の道である』とあるが、どのような人間になれるか」と聞かれました。自分個人の考えですと断り、「素直な人、利他(相手の心を読む)、奮起、楽観」と話をしました。イギリス人との話ですので、私の下手な英語で何度も話をし、大変喜ばれたことがあります。繰り返しますと、素直な人が剣道が強くなります。また相手が何を考えてるか読める人は、今の社会でも大変必要です。
利他(相手の考え)は?仕事の場合、その他色々と、理解しあうのに必要です。「利他」は具体的に云いますと、仕事、セールスマンでも技術者でも相手のことは大事です。技術者は次の世代にどのような機械が必要なのか、人々を読み、明日を読むのは大変必要なことです。楽観は、「一度や二度失敗しても頑張れば次はうまく行く。」とお話しますと大変な人気となり、3日間の講習会・稽古会で初日30人、2日目50人、3日目80人となり、同じ話を繰り返しました。
「事理一致から事理相忘へ!」事理を求めて旅へ出て、気が付けば事理の一致は後の方にあり、今は事理相忘です。「事理相忘!」剣道で事理相忘とは打たれて喜ぶ。大変難しいです。
私は「出来るだけ正しい剣道とは?正しい構え、技、気力、気剣体(理法)が大事です」と話しました。出来るだけ多くの人に、できるだけ多くの方法で楽しい時間を過ごしました。
素晴らしい剣道を!(受付日:令和6年8月2日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。