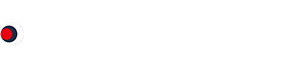図 書
剣術歴史読み物
第4回 藤田東湖の実用剣術論
南山大学 名誉教授
榎本 鐘司
江戸時代、幕藩体制のもとにあっては、基本的に「身分」がすべてを左右した。中でも武士の「家格」は細かく規定され、家格によってその職分が決定してしまう家業世襲の社会であった。
これが崩れるのが18世紀末からであり、19世紀に入っていよいよ幕末となると、人材の登用は盛んで、実力主義の時代となる。この時に、立身出世の手段に成り得たのが剣術であった。
幕府が武術振興策を打ち出すのは寛政改革のころからで、それに一層の拍車がかかるのが天保改革の前後、この頃から諸藩に軍事改革の動きが活発化して、旧来の武術流派を廃して、新たな武術流派の需要が生じた。実力主義による人材登用ということになり、ここに撃剣(試合剣術)流派の剣術家が、諸藩の剣術教授役として採用されていったのである。
この時、士農工商、あらゆる身分の者たちが剣術界に参入し、その業を競う時代が到来し、「剣術熱」と云っても良いほどのブームであった。
確かに、ペリー来航を経て、実際の戦闘に威力を発揮するものが西洋式の銃・大砲であることが明らかとなり、したがって、剣術の軍事技術としての実用性を真正面から議論は出来なくなる。とくに弓術、そして剣術や槍術といった旧来武術にかかる実用論は、軍事政策論としてはすでに本筋の問題ではなく二次的なものとなったのであるが、これでも「剣術熱」は治まらず、諸藩での剣術家の登用も盛んであった。
このような「剣術熱」を後押し、旧来武術の実用論を熱く主張したのが、かの徳川斉昭であった。
「槍剣手詰めの勝負は神国の長ずる所」(嘉永6年7月10日「海防愚存」)として槍術・剣術の白兵戦での有効性を述べたのである。幕府の能吏たちもこの斉昭の主張には逆らえない。
さて、斉昭がこのように主張する真意はどの辺りにあったのであろうか。斉昭の側近であった藤田東湖が天保15年(1844)に著した『常陸帯』に次のようにあることに注目したい。
「そもそも神国の武勇万国に勝れ、中にも刀槍の術の強く鋭きこと、蛮夷戎狄等の企て及ぶべき所にあらず、(中略)今の世の如く、刀槍の藝盛なる事昔よりためしある可からず。是試合といふもの始まり、実用をはげみ勤むるによりて、人の胆気定り、筋肉堅くたのもしく、其技精絶なるゆえんなり。」
「面小手を用ふれば剛堅に作れるしなひもて、(中略)其わざ鋭く、手足身体も鍛ひたる如く堅まり、雪霜の中に汗を絞れる許に戦ひぬれば、気息も長くなりて終日戦ひても疲れざるに至る」
「我が藩も今は専ら刀槍の試合行われ殊に弘道館出来ぬる後は、鬼の子の如き少年、むれむれ出でくるぞ心地よき。(中略)少年の人々、仮そめにも、君の御志を忘れず、大和魂をみがきて、槍太刀のわざをな怠りそ。」
水戸藩弘道館での稽古が、従来の袋撓を用いての剣術稽古から堅固な防具としないを用いて十分な勢いで打ち込む稽古に変わって、少年たちの筋力、体力、気力が充実し、「鬼の子の如き少年」がどんどんと出てくるようになったと述べている。すなわち東湖は、試合剣術は微弱にながれる武士の体力・胆力を強化するのに大変効果的であると言うのだが、ここに指摘される試合剣術の体練的効果こそが、剣術や槍術にかかる「実用」の問題として認識されていたことが重要な点である。斉昭も、近接した白兵戦における剣術の実用性を述べながらも、「強兵」化する手段としての剣術の効用を十分に認識していたのである。
ところで、幕府講武所剣術師範役であった男谷精一郎は、「実用的」な試合剣術とするためには、しないの長さを適切なものとしなければ成らないことに苦慮する。その結果、講武所では「三尺八寸」という長さのしないに統一された。腰刀の三尺三寸程度の長さでは、激しい打ち込みができずに体練的効果が損なわれることへの危惧があったからである。男谷精一郎のこの決断は、彼は剣術家でもあったがそれ以上に旗本幕臣であり、職分に忠実で有能な、東湖と同じ能吏であったことの証明でもある。
(つづく)
*この剣術歴史読み物は、2002年5月〜2003年7月まで3名の筆者によりリレー形式で15回に渡り月刊「剣窓」に連載したものを再掲載しています。