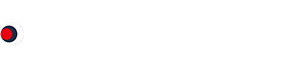図 書
剣術歴史読み物
第8回 ナショナリズムと剣術――剣術の意義づけと普及
天理大学 名誉教授
湯浅 晃
明治10年代後半から、維新以来の政治、文化あらゆる面での欧化一辺倒の風潮に対して反動の機運が高まった。そのようなうねりは、明治20年を境に一挙に堰を切り、新たな思想・文化が花開いた。とりわけ、志賀重昂、三宅雪嶺、陸羯南らを中心とする国粋主義を唱えるグループは、徳富蘇峰を中心とする「平民主義」とともにこの時代の思想界をリードした。
彼らは「国粋保存旨義」(国粋主義)を説き、民族の独自性の発揚を強調した。しかし、後年の高山樗牛らの「日本主義」(国家主義)と比べるとき、欧米文化の排斥や、日本の「開化」を否定するものではなく、むしろ欧米文化に対する没批判的な自主性を欠いた摂取という、当時の日本の開化のあり方であった。つまり、〈日本的なもの=古くさいもの・悪なるもの〉であり〈西洋的なもの=新奇なるもの・善なるもの〉という文明開化的な風潮に対する批判であった。西洋の優れたところは積極的に採り入れるべきであるが、日本古来の文化にも評価に値するものがあるはずであり、それを見失わず発展させることが日本の文化的アイデンティティを確立し、国民国家として西洋の一等国に肩を並べるために必要であると主張した。
彼らの思想は、日本の文化の進路にも一つの反省を呼び起こし、伝統文化の革新、ないし民族文化の再発見を促した。正岡子規の俳句革新運動は、彼らの影響を直接受けたことで知られる。
武術のなかで、この時代の国粋主義的風潮に最も合致したかたちで、伝統文化の再構成を図り成功した例として嘉納治五郎の「講道館柔道」を挙げることができる。嘉納は日本の伝統的柔術を西洋の近代主義的思想をもって合理化・科学化を図り、近代国家における青少年の教育材として近代「柔道」を創出した。
剣術においても、明治21年以降の剣術書執筆者の意図は、復興しつつある剣術を初心者、とりわけ小学校・中学校の児童・生徒に対して普及させていこうとするものであった。そして、剣術と対照をなすものは、明治初年から学校教育に取り入れられた西洋式「体操」であり、興味関心や日本人との相性の点で剣術の優位性を主張しながらも、指導内容や方法においては「体操」の医学・生理学的合理性を採り入れていくという、和洋折衷もしくは「接ぎ木」の時代に入ってゆく。
数巻の剣術書に即してみれば、『武道剣法手引草』(明治21年)の著者清水國虎は、先人から学んだことを「弟子ノ小童輩能ク知リ易」いように指導上の工夫し、生理学的見地から旧来の指導方法見直し、効率的な指導方法への脱皮を試みた。そして「体操」については、その身体的効果は認めながらも、「学齢期ヲ過ギ各其事業ニ従事スル諸氏ニ於テ、曽テ体操術ノ行ハルヽヲ聞カズ。(中略)今ヤ体操術ノ実地ヲ講ゼント欲セバ、我国固有ノ撃剣武術ヲ学ブヨリ先キナルナシ」といって、生涯体育的な観点から武術の優位性を主張した。また『撃剣教育論』(明治24年)の著者日比野正吉も、外国人医師ベルツとおぼしき人の助言をもとに、西洋伝来の体操やスポーツに対する剣術の優位性を説き、「撃剣教育を主とし、撃剣教育の足らざるところを、今の教育法をもって補ハん」という姿勢を明確に打ち出している。
坂似水著『剣法遺伝』(明治22年)は、「遺伝」という書名が示すように近世的心法論への極めて強い回帰性をもっており、この時代においてはかえって異色といえる。その回帰の行き着くところは白井 亨や寺田宗有、針谷夕雲にまで至っている。しかし、回帰を主張する一方で、「ステッキ術」という剣術の新たな方向性を提唱していることに本書の意義がある。このステッキ術は、護身術への剣術の質的転換を意図したものといえるが、剣術が近代社会のなかで容認されるには、剣術が原初的にもつ暴力性、そして「しない剣術」(撃剣)がもつ遊技性の両者を排除する必要性を認識していたものと思われる。
〈近代社会における剣術の意義づけと普及〉、これが明治20年代、剣術関係者の最大の課題であったことは間違いなかろう。
(つづく)
*この剣術歴史読み物は、2002年5月〜2003年7月まで3名の筆者によりリレー形式で15回に渡り月刊「剣窓」に連載したものを再掲載しています。