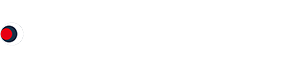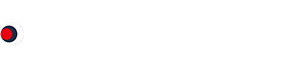図 書
幕末在村剣術と現代剣道
最終回 赤城山麓の念流・本間千五郎應次の巻
全剣連 広報・資料小委員会 委員
工学院大学 教授
数馬 広二
今回は幕末期に武者修行者たちから一目置かれた道場―赤城山のふもと「本間道場」―の道場主であり、古伝の流儀に撃剣(竹刀打ち剣道)を採用した、本間應次(1816~1889・千五郎)について述べてみます。
本間應次の家は、鎌倉時代、佐渡国の守護であった本間能久を遠祖とし、1589年上野国佐位郡市場村(現・群馬県伊勢崎市市場町一丁目。前・赤堀町)に帰農し、能久以来31代続く家でした。
應次の祖父・仙五郎(應郷)は、蓄財の才に優れ「本間大尽」と呼ばれ、広さ六反(1800坪)の屋敷地に自宅道場「練武館」を建てました。その仙五郎は、5代前から継承される浅山一伝流居合を修め、荒木流(捕手・小具足・居合・縄)の極意に達したのち馬庭念流に入門し、宗家から3名のみに与えられた「永代免許」を授かり、その流派は「赤堀(本間)念流」とも言われました。仙五郎が没すると、應次の父・應吉が道場を引き継ぎますが、古流道場としての本間道場にも撃剣流派の勢力が押し寄せてきつつありました。この頃(1816年)に應次が生まれたのです。
應次が8歳(1823年)の時、江戸から上野国へ弘流してきた北辰一刀流の創始者・千葉周作が、伊香保神社(現・群馬県渋川市伊香保町)へ流儀の額を掲げようとしました。父應吉が奉額阻止のため急支度をして門人17名と共に伊香保に出陣する姿を、應次は目の当たりにします。代官の仲裁によりこの一件が落着した後、應次は父應吉から念流剣術、荒木流柔術、一伝流居合を学び始めました。
修行を重ね三術に達した應次は、29歳(1844年)で、父・應吉が隠居し、本間道場主を襲名することになりました。襲名を記念する門人姓名額奉納の行事が、近村の雷電神社(現・伊勢崎市西久保町三丁目・大雷神社)で執行されました。その時、「道場世話人総代」の板野安蔵から「腹巻」(戦陣で使う胴)を着用した竹刀打ち試合を「内々に」許可して欲しいという願い出(「以二書面一奉願上候」)が應次へ提出されたのでした。
撃剣防具が発明されてから約90年、形稽古中心の馬庭念流を継いで3代目の應次は、門人らの願いを聞き入れ、防具着用の撃剣稽古法の採用に踏み切りました。
その後、直心影流島田虎之助門人、同流男谷精一郎門人、長竹刀で江戸の道場を席巻した大石神影流門人、示現流門人、甲源一刀流門人、一刀流中西忠兵衛門人、北辰一刀流千葉門人、心形刀流伊庭軍兵衛門人ら、名だたる撃剣流派の門人が本間道場を来訪し、稽古や試合をしました。その試合方法は、両名の取得合計が3本あるいは10本に達するまでの勝負でした(『嘉永四年稽古順着帳』)。
さて、撃剣稽古を取り入れた應次(34歳)は、一方で馬庭念流宗家から「矢留術」の免許を得ました。「矢留術」は、馬庭念流中興の祖・樋口又七郎が、師・友松偽庵から1596年に伝授され(『念流未来記目録犬巻』)、撃剣流派に押され自流の門人が減少気味であった折、宗家・樋口定伊が1844年頃に、流儀の命運をかけて再興した技でした。「堅甲厚冑をたのむ(堅くて厚い甲冑をあてにする)業は盡く虚用」とし、十間(約18m)離れたところから射られた弓矢を素肌で構えた木刀で真っ向から切り落とし止めるこの技を、定伊は1849年(嘉永2)4月、水戸藩徳川斉昭の御前で披露し、「実地に通合する」と絶賛され(『馬庭念流代々記』)たのです。
應次は、撃剣稽古を採用したものの、「命がけ」の臨場感を追体験する必要性を感じ、この矢留を修錬したのかも知れません。
だとすれば、その後應次が「面小手之上、試之儀、自他流差別無く、情心を尽くし修行致す可き」(『萬控記』)と奨励した、撃剣による武者修行もまた、「命のやりとり」を前提としていたのでしょう。
撃剣への脱皮を苦心する應次の遺志は、明治期に撃剣興行で活躍した田口永八郎や、大正期に剣道範士となった應次の子・本間三郎など、古法の精神性を維持しながら撃剣に取り組んでいった門人に受け継がれたのです。
◆ ◆ ◆
「命のやりとり」を前提としながら真剣に生きてきた剣術家の姿を、江戸時代幕末期の在村剣術にみてきました。村社会に支えられてきた撃剣流派の活動が、近現代の社会形成にどのような役割を果たしたかについては、今後の課題としたいと思います。
(おわり)
*この幕末在村剣術と現代剣道は、2006年4月〜2006年9月まで6回に渡り月刊「剣窓」に連載したものを再掲載しています。