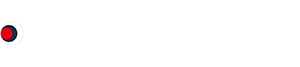審査会
更新
居合道七段審査会(京都)
- 開催日:
- 2024年03月03日(日)
- 会場名:
- 京都市武道センター
審査会結果
審査員の寸評(実技)
3月3日(金)、京都市武道センターにおいて標記の審査会が実施された。真砂 威副会長の挨拶で、今回から第一・第二会場同時に高齢者から順に審査を進める方針の説明があった。中谷行道専務理事からは海外渡航中の審査会について、草間純市居合道委員長からは指定技の着眼点と審査に臨んで、注意事項の説明を受けた。
指定技は、各段共通で一・三・五・九・十・十一であった。総合的に感じた事は、
①自分を生死を懸けた状況に置いていない。長岡藩士の精神規範「常在戦場」を心してください。
②刀に振り回されている。刀を身体の一部として自由自在に使いこなすことで、上半身の力みがなくなることと思います。
③一つの動作ごとに居着いてしまう。次の動作のための余裕と気の流れをつなげる必要があります。
④風格・錬度は稽古の質と量で鍛えられるものと思います。
一本目「前」省略
三本目「受け流し」指定技に「受け流し」が出たときは、重要な判断基準となろうかと思われます。振り回しではなく受け流しができているか。右肩上方では刃波で袈裟に切る方向になっているか。袈裟切りと斜め切りは違います。
五本目「袈裟切り」切り上げる時の刀身と刃先の方向が違う。抜き出す方向、鞘を返す角度。三本目同様、右肩上方での刃先の方向を見直してください。
九本目「添え手突き」抜き打ちは、肩口から脇まで切り落とす事が目的です。刀を抜くだけではない。突きは、刀を引くところから始まります。上腰にとってからの突きでは間が生じます。
十本目「四方切り」四方切りは、四方向に向かって刀を振るのではなく、至近距離にいる四人の敵を切り倒す間合感覚を身に着けてください。流れの中での脇構えの意味を表現してください。
十一本目「総切り」一本ごとに気が居着くことなく一気呵成に技を終える。切っ先の軌跡と気の流れを何度も繰返し稽古してから審査に臨んでください。
段位は、上がる度に義務と責任が重くなります。段位にふさわしい稽古と指導力が要求されます。正しい居合を伝えるために、自ら試行錯誤しながらの研究を続けていかなければなりません。
行事概要
- 行事名
- 居合道七段審査会(京都)
- 開催日
- 2024年03月03日(日)
- 会場名
-
京都市武道センター
〒606-8323 京都府京都市左京区聖護院円頓美町46-2
市バス「熊野神社前」下車、東へ徒歩1分 市バス「京都会館美術館前」下車、北西へ徒歩3分